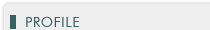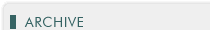志賀泉の「新明解国語辞典小説」
- あ
- 09/07/07
- い
- 09/07/30
- う
- 09/08/15
- え
- 09/08/31
- お
- 09/09/13
- か
- 09/09/24
- き
- 09/10/08
- く
- 09/10/28
- け
- 09/11/19
- こ
- 09/12/03
- さ
- 09/12/13
- し
- 09/12/27
- す
- 10/01/24
- せ
- 10/02/15
- そ
- 10/03/04
- た
- 10/03/24
- ち
- 10/04/12
- つ
- 10/05/03
- て
- 10/05/16
- と
- 10/06/04
- な
- 10/07/01
- に
- 10/07/15
- ぬ
- 10/08/02
- ね
- 10/09/01
- の
- 10/09/20
- は
- 10/10/03
- ひ
- 10/10/31
- ふ
- 10/11/22
- へ
- 10/12/24
- ほ
- 11/01/23
- ま
- 11/02/22
- み
- 11/03/15
- む
- 11/04/24
- め
- 11/05/24
- も
- 11/06/20
- や
- 11/07/28
- ―
- ―
- ゆ
- 11/09/14
- ―
- ―
- よ
- 11/10/30
- ら
- 12/01/24
- り
- 12/01/24
- る
- 12/01/24
- れ
- 12/05/01
- ろ
- 12/05/01
- わ
- 12/07/09
- ―
- ―
- ―
- ―
- ―
- ―
- ん
- 12/07/09
ん
んだ
12/07/09
んだ
〔東北・関東方言〕相手の発言を肯定する気持ちを表わす。
んだ。=肯定
んだな。=同意
んでね。=否定
んだべが。=疑惑
んだべした。=強調
んだべげんちょも。=反論
んだがもしんにげんちょも。=強い反論
んだ。この肯定は苦い。「ん」で口を結び、肯定する事柄をぐっと腹に呑み込み「だ」で吐き出すように断定する。
んだ。肯定しながら、半ば口籠もる。口籠もりながら、語気は強い。怒りも、諦めも、悲しみも、「んだ」の一語で噛み締める。「んだ」は、耐え難いことにも耐えてきた東北人の、苦い苦い肯定なのだ。
んだ。んだがらよ、夢さじいちゃん出てきて、家はおらが見守ってからおめは心配すんなと、こう言うだべ。んだな。いぐら心配したって家さ帰らんにではどうにもなんねし。空き巣がきたらじいちゃん化けて出ておどがしてくいんのがな。あいや、頼もしごど。
んでね。おらほはそんなに放射線量は高くね。道で警察官が見張ってっから中さ入らんにだげだ。入ったってさすけねよ。政府の言うこと聞いてだら死ぬまで入らんによ。
んだべが。政府の言うことはそんなに信用でぎねだが。
んだべした。政府のおかげでわざわざ放射線量さ高えとこに避難させらっちよ。自分の家さいだほうが安全だったがもしんねのに、ごせやげっこと。
んだべげんちょもよ。放射能なんかおらみでえな年寄りにはさすけねど。どうせもう寿命は残ってねえがら同じことだべ。おらさっさと家に帰りで。
んだがもしんにげんちょもよ。一人で帰ったってさびしだげだよ。じいちゃんいるって、じいちゃん死んでっぺした。いいがら、家のことはじいちゃんにまがせどけ。
んだ。じいちゃんにまがせどげ。
んだな。死んだじいちゃんでは話し相手にはなんねもんな。
んだ。生きてる人としゃべったほうが寿命も延びっちしな。
んだんだ。
んだんだ。
わ
をや
12/07/09
をや
〔雅〕①〔格助詞「を」+副助詞「や」〕その動作・作用の及ぶ対象を特に強調して示す。②〔終助詞「を」+終助詞「や」〕感動の気持をこめて文を終始することを表わす。③〔終助詞「を」+副助詞「や」〕比較的程度の軽い前件と対比して、後件は問題なく成立することを表わす。
「日本の文学は言文一致体になって頽廃しました」
なに言ってんだよ。意味わかんねえよ。
俺はよ、小説の書き方を教えるっつうからこの授業をとったわけ。「小説創作科」っていったらそういう意味だろ、ふつう。俺はライト・ノベルの作家になりてえんだよ。いじめられっ子がふとしたことで特殊な能力を身につけ謎の美少女に助けられながら冒険するっていう、そういう夢あふれる小説のね、ストーリーはできてんだけど文章にできねえから勉強しようと思ってこの授業とったんだけどおい、おいおい、あれが先生かよ、どこの老人ホームで見つけてきたんだよ。ったく、てめえは遺書の書き方でも教えてろっての。俺はファンタジー大賞を狙ってんだからさ。
「いわゆる口語体。これがいけません。日本語が本来持っていた艶、色艶の艶ですね、この艶が口語体の登場で失われてしまいました、永遠にです」
でさ、俺のはさ、ただのファンタジーじゃないわけ、深いんだよ、ちゃんと。ある王国のね、お姫様が革命軍に拉致されてね、それで主人公が助けに行くわけだけど武器が足りなくてさ、それで盗賊一味と手を組もうかって話になるんだけど盗賊って悪人じゃん。そこで主人公は悩むわけ。正義とはなにか、とかね。そっから先はいま考え中だよ。
「たとえばです。『善人なほもちて往生を遂ぐ、いわんや悪人をや』この言葉を現代文に訳してごらんなさい。ほれ、そこの君」
うわっ、びっくりした。一瞬指されたかと思った。隣の席だったよ。紙一重でかわしたってやつだね。次、俺くんなよ。後ろにいけ後ろに。間違っても右くんなよ。あ、よし、後ろにいった。とうぶん安泰だな。しかしまあ、小説家になりたいって奴は馬鹿ばっかりなんかな、高校のとき習ったろ、有名だぜこの言葉。親鸞だよな、たしか。あれ、違ったっけ。法然だっけ。日蓮は違うよな。日蓮はナムミョウホウレンゲキョウだもんな。
「ああ、駄目ですね。ぜんぜん駄目です。現代文に訳しては、どうしても親鸞の思想は伝えきれません」
ああ、やっぱ親鸞でよかったんだ。頭いいよな俺って。それよっか俺の小説だよ。主人公が盗賊と手を組むかだよ。わははは、正義のためには悪に染まることも必要なんだよ。お、いいねこのセリフ。忘れないようノートに書いておこ。
「いいですか。重要なのは『いわんや悪人をや』の『をや』です。この二文字に親鸞の思想が凝縮されているといっても過言ではありません。そこの君、『をや』を現代語にしてみなさい」
「え、俺?」
「『をや』をどう訳しますか?」
「いや、違うだろ。順番でいったら次あいつだろ。なんでいきなり俺を指すんだよ」
「なにを言っているのですか、あなたは」
「だから順番が違うだろって言ってんだよ。あいつが答える番なんだよ」
「ああ、もうけっこうです。わかりました。もうあなたを指しません。永遠にです。だからご安心ください」
なにが永遠だよ。老い先短いくせに。てめえの永遠はあと四、五年ってとこだろ。それよっか俺の小説。あれ? わははは、の次なんだっけ? なに書こうとしたんだっけ? わははは、いわんや悪人をや。違うな。くそう、先生が急に俺を指すから。
「君の名前は?」
「は?」
「君の名前を聞いているのです」
「うっせえんだよ、このジジィ」
うわっ、軽く押しただけなのにすっ飛んじまった。死んでねえよな。あ、生きてる生きてる。よかった、あやうく殺人犯になるとこだったよ。小説のためなら先生も殺すってね。悪人だな俺は。善人だって小説を書く、いわんや悪人をや、だよ。
わ
わなわな
12/07/09
わなわな
恐怖などのためにからだが小刻みに震える様子。
まあ、想像してほしい。朝、着替えようとしてタンスを開けたら、吊り下げた洋服の間で見知らぬ女の子がうずくまっていたとしたら、どんなに驚くか。
あり得ない? でも現実にそれは起きた。どんなに妙なことでも、起きたことは起きたこととして、冷静にこれを受け入れなければならない。
彼女は二十歳前後、髪が長く、水色のワンピースを着て、肌の色もワンピースに似て青白い。よく見れば剥き出しの肩が小刻みに震えていた。
どこから入ってきたのか。どんなに記憶をひっくり返しても部屋に招き入れた覚えはない。酔っぱらって連れ込んでおいて忘れたとも考えにくい。昨夜はしらふで帰ってきたのだ。かといって泥棒にも見えない。だいいち僕のマンションはセキュリティが万全で、そうやすやすと侵入を許すシステムではない。
「もしもし」僕は声をかけた。「もしもし、そこでなにをしているのですか」
いくら怪しくても相手は女の子だ。乱暴には扱えない。
「すいません、追われているのです。かくまってくれませんか」
かすれた声で彼女は懇願した。その声が真に迫っていたので、念のため僕は部屋の中をぐるりと見渡した。
「特に変わった様子はないけど」
「タンスの中に置いてもらえればいいのです」
「まいったなあ」僕は鼻の頭をぽりぽり掻いた。「かまわないけど、僕はこれから着替えて会社に行かなくちゃならないんだ。ちょっとどいてもらえないかな」
「あ、すいません」
彼女は膝をぎゅっと抱えて小さくなった。折りたたみ椅子をたたむように、膝を抱えた彼女はちょっと信じられないくらい薄くなった。
それで僕はワイシャツとネクタイとスーツを取り出し着替えることができたのだが、その間も彼女は肩を震わせていた。
彼女はなにに怯えているのだろう。君は誰で、誰に追われていて、どうやってこの部屋に入ったのか、いくら尋ねても答えてくれない。しかし、だからといって無下に追い出すわけにもいかない。僕のせいで彼女が殺された、なんてことになったら嫌だもの。
「じゃあ、僕は出かけるけど、誰かに押し込まれそうになったら玄関横に防犯スイッチがあるからそれを押すといい。三十分以内に屈強な警備員が駆けつけてくれるはずだ」
侵入者に防犯システムを説明するのもおかしな話だが、成り行き上やむを得ない。
僕はタンスの扉を閉めた。「ありがとうございます」とか細い声が聞こえた。
会社の同僚に今朝の出来事を話すと、同僚は「ああ、それは妖怪わなわなさんだね」と、なんでもなさそうに言った。
「妖怪わなわなさん?」
「座敷わらしみたいなもんさ。気にしなさんな」
「しかし、いくら妖怪とはいえ洋服ダンスに女の子がいるのは落ち着かないな」
「その女の子に見覚えはないの?」
「ないよ」
「ほんとに?」
「ほんとにないったら」
「それはどうかな。忘れているだけかもしれないぞ」
同僚は含み笑いを浮かべた。僕は軽く腹を立てた。だいたい、彼女はやせっぽちで、いかにも貧相で、ぜんぜん僕の好みでないのだ。
「彼女はなにに怯えているのだろう」
「それは愚問というものだ。妖怪あずき洗いにどうしてあずきを洗っているのか尋ねるようなものだ」
同僚が言うには、わなわなさんは無害な妖怪で、福を呼びもしないかわり災いをもたらしもしない。放っておけばいつの間にかいなくなるということだった。
夕方、帰ってみると部屋に異常はなかった。玄関にもリビングにも荒らされた形跡はない。ほっとしながらタンスを開けてみると、中にはやはり、女の子がうずくまってわなわな震えていた。彼女はどこから見ても生身の人間で、とても妖怪には見えない。
「ずっとそこにいたの?」
普段着に着替えながら彼女に話しかけた。彼女はこっくりうなずいた。僕はそっと彼女の顔を盗み見た。やっぱり見覚えはない。
スーツをタンスにしまおうとすると、彼女はぎゅっと膝を抱き寄せ体を折りたたんだ。妖怪なりに遠慮しているらしい。
「誰も押し入ってはこなかったんだ」
「はい、おかげさまで」
「じゃあそこから出てきてもいいんじゃないかな」
「いえ、まだ安心はできません」
「気が進まないなら、僕も無理には引っ張り出さないけど」
「ありがとうございます」
たしかに無害そうではある。
僕は台所で料理を作り、テレビニュースを見ながら食事をし、ビールを飲み飲み借りてきた映画のDVDを見ていたが、その間タンスの中からはことりとも音がしなかった。もう消えてしまったのだろうか。気になって扉を開けてみたら、まだいた。膝頭にのせていた額を起こし、「お出かけですか?」と、膝を抱き寄せた。
「あ、いや、僕はもう寝るからね。おやすみを言おうと思って」
「あ、はい」
「なんならソファで寝てもかまわないけど」
「いえ、油断はできませんから」
彼女は細長い指で自分の肩を抱き、わなわな震えた。扉を閉めてタンスに背を向けてから、「おやすみなさい」と消え入りそうな声が聞こえた。
その夜はなかなか寝つけなかった。「見覚えはないの?」という同僚の言葉が気にかかり、中学時代から今日までの、僕が付き合った、あるいは付き合ったとは言えない、遊びで終わった女性や一夜限りの女性も含めて片っ端から思い出してみた。どの顔も彼女に似ていなかった。しかしそれは同時に、どの顔も彼女に似ているとも言えた。
ふと、人の気配がして目を開けた。彼女が金属バットを振りかぶり枕元に立っていた。「え?」と声を上げる間もなく、金属バットが顔面めがけて振り下ろされる。僕は咄嗟にかわしてベッドから転げ落ちた。彼女の金属バッドが執拗に僕を追った。ワイングラスが割れ、ステレオ装置が砕け、目覚まし時計がはじけ飛んだ。「おい、ちょっと、待て、君は無害のはずだろ」抗議をしようにも声が出ない。僕は転げ回り、逃げ惑い、寝室の角に追い詰められた。彼女の金属バッドがうなりを上げる。僕は頭を抱えてうずくまる。頭蓋骨に鈍い衝撃を覚えた。次の瞬間、目が覚めた。
夢だった。僕はベッドの上にいた。寝室はしんと静まり返っていた。
翌朝、タンスを開けてみると彼女は吊り下がった洋服の間できちんと膝をそろえて正座していた。
「ありがとうございました。もう大丈夫です」
彼女は深々と頭を下げた。
「ああ。それはよかったですね」
よかったとしか言えない。昨夜の夢のことは黙っていた。
「たいへんご迷惑をおかけしました。ご親切は忘れません」
彼女はタンスから足を下ろし、ゆっくりと背筋を伸ばして玄関に向かい、いつの間にか手にしていたハンドバッグからハイヒールを取り出し足にはめると、妖怪らしからぬ礼儀正しさでもう一度深々とおじぎをし、ドアの外へ去っていった。
リビングに戻ると、いつの間にかテーブルの上にスルメが置いてあった。お礼のつもりだろうか。
わ
わたつみ
12/07/09
わたつみ
〔「わた」は海、「つ」は「の」に当たる雅語の助詞、「み」は神の意〕海(を支配する神)。
「俺たちはみんな海の神の子孫なのさ」
そう言い切った君の強さはどこから来るのだろう。
アイルランドで漁師になりたいと君は言ったね。なぜアイルランドなのかは聞かなかったよ。いつもの大風呂敷だとばかり思っていたからさ。
だから君が銀行員をやめて漁師に転職したと聞いたときは本当にぶっとんだ。足が頭の上まで上がっちまったくらいだ。しかもアイルランドの寒さに慣れるんだとかで、東北の漁師に弟子入りしたんだから。おいおい、計画性と無謀さが背中合わせでダンスを踊ってるぜ。僕には「肝心なのは人生設計」とか言って預金通帳を作らせたくせに。
ところで君はアランセーターの伝説って知っているかい。アイルランドのアラン島のご婦人たちは、旦那が海に落ちて死んでも網目模様で身元がわかるようにって、手編みのセーターを旦那に着せて荒海に送り出したそうだ。まあ、これはあくまでも伝説であって事実ではないそうだが、それだけ漁師の仕事は死と隣り合わせってことだ。板子一枚下は地獄って、君も聞いたことはあるだろう。
「また見つかった。なにがって、永遠さ、海と溶け合う太陽さ」
東京の青山にあるアイリッシュ酒場で、ギネスビール片手に床を踏み鳴らしながら君はランボオの詩の一節を諳(そら)んじてみせたね。そういうきざったらしさが、君の憎らしさであり、同時に魅力でもあったのだけど。
去年の冬、洋子さんと僕とで君に会いに行ったことは憶えているだろう。あの日は海が荒れて漁は休みで、君は僕らを連れて行きつけの居酒屋に入り、地元でどぶ鍋と呼ぶアンコウ鍋をごちそうしてくれた。洋子さんはこういう店は初めてだっておどおどしていた。風が吹くと窓ががたがた鳴り、石油ストーブの上でヤカンがしゅうしゅう湯気を立てているような店は。それより驚いたのは君の変貌ぶりだ。余分な肉が削げて顔が引き締まり、目は精悍そのもの、無精ひげも様になって、すっかり狩猟民族だ。これが君の真の姿で、都会の銀行員だった君は仮の姿だったんじゃないかと思ったくらい。でもそれは君の適応能力の凄さであって、違和感のない東北弁を使って地元の人と冗談を交わしている君を見てると、アイルランドで漁師を始めてもきっとこんなふうにうまくやれるんだろうなと感心したものさ。
居酒屋を出て、火照った頬に刺すような北風を受けながら路地を抜けて港に出ると、のっぺりと暗い海面が上下に波打ち、接岸された漁船同士が揺れてぶつかりごんごんと鈍い音を立てるのを、洋子さんは「船のおしゃべり」と言った。君はわざわざ自分が乗っている漁船のところまで僕らを案内してくれたけど、はっきり言って迷惑だったよ。自分の吐く息があんなに冴え冴えとして見えたのは生まれて初めてだ。水銀灯の光に浮かび上がる白い船体が、吹きつける寒風に凍えて夜空に吠えているようで、「タラ漁はいまが最盛期で」なんて君の解説はちっとも耳に入らなかった。
海はどこまでも暗く、堤防に寄せては砕け散る波飛沫がしらじらと浮かんで、僕も洋子さんもそれがなんだか怖ろしくて、がたがた震えながら目を奪われていた。けれどその横で君は、自分の未来にばかり目を奪われていたんだよな。
そうさ、君は勇敢で、自由で、楽天家で、いつだって前を向いている。なあおい、君はあのとき、暗い海の向こうになにを見ていたんだい。
さっさと日本を離れてアイルランドに行っちまえばよかったものを。そうすりゃ津波なんかに巻き込まれずにすんだのに。
あの日、洋子さんが君にプレゼントしたアランセーターが、伝説どおりに身元確認の手掛かりになるなんて、悪い冗談だよ。セーターそのものは既製品だけど、洋子さんがその上から君のイニシャルを編み込んでいたんだってな。洋子さんは自分を責めていたよ。私がよけいなことをしたから死神を呼んだんだって。あの津波じゃあ、死神の出る幕もなかったと思うけどな。
あんなひどい死に方ってない、と洋子さんは泣いた。七日もたってから引き揚げられた車の中に君はいたんだ。どんな状態だったかは想像がつくだろう。
洋子さんは君の恋人ということで、君の両親から形見の品としてアランセーターを分けてもらい東京に持って帰った。何度となく漂白剤に漬けては干してを繰り返し、毛糸をほどいて編み直し、ふたつの毛糸帽に生まれ変わらせた。そのひとつを彼女がかぶり、もうひとつは僕がもらった。
ほら、見えるか。僕がいまかぶっている、この毛糸帽がそうさ。発見されたときに君が着ていた、あのセーターの毛糸で編んだんだ。結び目がところどころにあるのは、セーターが破れていたからさ。乳白色の生糸を染めている染みは、洗い落とせなかった君の体液だ。人が聞いたら気味悪いとかグロテスクとか陰口を叩くかもしれないけど、僕はそう思わない。毛糸帽をかぶっていると君を身近に感じる。君が死んだとは思えない。だって、死んだ人間に温もりはないはずだもの。
正直に言うと、僕はひどく落ち込んでなかなか立ち直れなかった。いや、悲しんでいるうちはまだよかったんだ。悲しみが抜け落ちた後の虚脱感のほうがひどかった。朝、目覚めるとなんにもしないうちから体が疲れ果てていた。毎日がそんなふうに始まった。電車に乗ってもどこかに寄りかかっていないと立っていられない。あれはしんどかったよ。いっそ病気になったほうが楽だと思ったくらいだ。
でも考えてみれば洋子さんのほうが僕の数倍は辛かったはずで、その洋子さんが僕に毛糸帽を渡して「海を見に行こう」と誘ってくれたときは、僕は洋子さんの強さに怖れをなしたものさ。
津波から半年が過ぎて、いまは夏の終わりで、君のいた街は津波に根こそぎさらわれてそっくり消えてなくなり、青草がぼうぼうに伸びてモンゴルの平原みたいだった。僕らは目を疑ったよ。モンゴルと違うところは漁船がごろごろと転がって遠くに水平線が見えることだ。君が住んでいたアパートも、どぶ鍋をつついた居酒屋も、どこにあったのやら、こうなってみるとさっぱり見当がつかない。ただ、以前は人の家の庭だったと思しきところにコスモスやらケイトウやらがまとまって咲いているのが、わずかに心を和ませてくれたけど。
堤防に立つと信じられないくらい海は穏やかで、打ち寄せてくる波を見ていると空っぽになった心になにかが満たされてくる思いがする。
なあ、そっちから僕らはどんなふうに見える? 季節はずれの毛糸帽をかぶった男女が堤防の上で肩を並べているというのは。
僕は毛糸帽を脱いで鼻にあてがう。深く息を吸いこむとかすかに異臭がする。それは、漂白剤でも消せなかった君の死臭だそうだが、生も死もあるもんか、君の体から染み出てきたものなら、それはやっぱり君の臭いだ。
なあ、君はどこにいるんだよ。僕はもしかすると、君よりも深く死んでいるんだ。
「また見つかった。なにがって、永遠さ、海と溶け合う太陽さ」
洋子さんは遠い目をして、墓碑銘を読むようにつぶやいた。
おい、永遠は見つかったか。ていうか、君が永遠そのものになっちまったんだよな。
ろ
ロイドめがね
12/05/01
ロイドめがね【ロイド眼鏡】
〔Lloyd=人名〕セルロイド製の太い縁をつけた眼鏡。
まんまるのレンズに黒くて武骨なセルロイドのフレーム。彼のお気に入りの眼鏡は、とっぽい。昭和の白黒映画に出てくるおじさんがかけていそうな眼鏡だ。
それもそのはず、世田谷名物のぼろ市で見つけた骨董品で、骨董品というよりがらくたで、昭和二十年代の品らしいが、古ければ価値があるというわけでもないだろう。ロイド眼鏡というそうだが、これが似合ってしまう彼もまた、とっぽい。
「永井荷風みたいだろ」と彼は言う。永井荷風という小説家がかけていた眼鏡に似ているそうで、それがつまり彼のお気に入りの理由だが、永井荷風という人自体がさほどイカしているわけではなく、もちろん荷風の時代にはダンディだったのだろうが、現代人の私から見ればとぼけたおっさんでしかない。
二千円の値札がついていたのを千円に値切ったと彼は自慢するが、私に言わせればそれでも高すぎる。こんなもの、道に落ちていたって誰も拾わない。
「買った時は度がきつくってさ。ぼろ市の人混みの中をぶつかりながら歩いて、しまいには頭がくらくらして吐きそうになった」
「無理しないで外したらよかったのに」
「いや、俺としては手に入れた時の感動を維持していたかったのよ。レンズを交換するのにメガネ屋に入るまでは意地でかけていたもんね」
ばかみたい、と私は心の中でつぶやく。ばかみたい。どうでもいいことに意地をはるのが彼の癖。生き方、と言ったら大袈裟か。もちろん上手な生き方ではない。
彼は三流大学の文学部を出ていて、いちおう夢は小説家らしく、ちょろちょろとしょぼい短編を書いている。でも書きっぱなしで新人賞に応募することはない。じゃあなんのために書くのかと聞けば「自給自足」だという。自分で読みたい小説を自分で書いて悦に入る。つまり自己完結しているわけだ。
あこがれの小説家は永井荷風。娼婦との交情を書いた小説家だ。なぜ好きかと聞いたら「洒脱」と彼は答えた。彼はとても洒脱に見えないけれど。でも飄々とした雰囲気は荷風と似ているかもしれない。
ぼろ市で彼がロイド眼鏡を手に入れた時、私は彼のそばにいなかった。彼のそばにいたのは私の知らない女の人だ。その人はロイド眼鏡をかけた彼にどんな感想を述べたのだろう。歯の浮くようなお世辞を並べてさんざんおだて上げ、どんどん木に登らせてついには下りられなくさせたのだろうか。私が知っているのは、年上で背の高い女というだけだ。色っぽくて、水商売系で、というのは私が勝手に加えた想像だ。
ぼろ市の雑踏を、度の合わない眼鏡をかけてふらつく彼の手をとり、人波を割ってずんずん歩く派手めの女を私は思い描く。別れた理由は知らない。理由がなくたって人は別れる。私が彼と出会ったのは、彼がその女と別れてしばらくしてからで、その時すでに彼はロイド眼鏡を四六時中かけている人になっていた。
どうせ永井荷風にあこがれているならレトロに徹してソフト帽でもかぶっていればまださまになっていただろうが、出会いの場面で彼がかぶっていたのは焦げ茶のニット帽で、ロイド眼鏡との相乗効果でなおさら彼をとぼけた顔に見せた。ぬうぼうとして、とらえどころのない彼に、私はつい油断してしまった。いい人かもしれないと思った。私は二年間付き合った人と別れたばかりだった。
初めて彼と寝た時、彼は裸になっても眼鏡をかけていた。シャワーを浴びた彼は、全裸に眼鏡という格好で浴室から出てきたので、先にベッドに入っていた私はびっくりした。
「はだか眼鏡」と私はからかった。「はだかエプロンってあるでしょ。あれの眼鏡バージョン。はだか眼鏡」
「はだかエプロンってしたことある?」
「ないわよ。あるわけないでしょ」
「今度してみてよ」
「いやよ。エプロンだって持ってないのに」
「眼鏡がないと正面と背中の区別もつかないんだ」
「それって、女性に対してすごく失礼」
「顔だと思ってキスしたらそれが足だったりする」
「顔がこんなことする?」
ベッドに寝そべったまま、私はつま先を跳ね上げて彼のお腹を蹴ってやった。
彼は私の脚を広げながら、ロイド眼鏡をはずしてそっと腕を伸ばし、私の顔にかけたのだった。視界が薄ぼんやりとして、それはすごくエロチックな行為に思えた。けれどそれだけに、なんだか嫌な気分が込み上げもしたのだ。彼は、前の女ともこんな戯れをしていたのだろうか、そう思うと堪らなかった。知らない女が私に乗り移ってきて、私が私でなくなっていくような気がした。声をあげても、自分の声でないような気がした。
私は特に彼を好きというわけではなく、寂しかっただけかもしれない。付き合っていればだんだん情が移っていくだろうと期待したし、実際そのとおりになりかけていたけど、心の芯は冷めていた。心の底から好きというふうにはなかなかなれなかった。それは秘密だった。でも、彼だって同じはずだと勝手に決めつけ、お互いさまだと思い込もうとした。私はずるいのかもしれない。
彼のロイド眼鏡が実は度の入っていない伊達眼鏡だと知ったのは、彼と付き合い始めて半年ほどたってからのことだ。喫茶店でたまたま出会った彼の友達が教えてくれた。
「あれ、知らなかったの?」
友達は心底意外そうな顔をして、それから空気がとても気まずくなった。なんだか、知ってはならない秘密を知ってしまったような気がした。
「だって、目が悪いって言ってたし、運転免許証の写真だって眼鏡をかけてるし。更新のときに視力検査をしたわけでしょ」
「検査で嘘をついたんだよ。徹底するからな、あいつは」
私が彼の眼鏡をかけたのは、彼と初めて寝た時の、あの一回きりで、たしかにあの時はぼやけて見えたはずだが、よくよく考えてみるとあれは、レンズが彼の息で曇っただけだったのかもしれない。
ショックだった。何者なのだ、あいつは。ほとんど意味のない、どうでもいい嘘なだけに、彼という人間がわからなくなった。このていどの嘘も見抜けなかった自分自身も信じられなかった。私はいったい彼のなにを見ていたのだろう。
「でも、伊達眼鏡ってふつうおしゃれでするものでしょう。ぜんぜんおしゃれじゃない」
「そこがあいつのひねくれ者たるゆえんだ」
「私、だまされてたのか」
「あ、いや、だましている意識はないと思うよ。たださあ、なんていうか、あいつは昔っからああいう奴なんだよ。深い意味なんてないんだよ」
「わかってる。ただ、あんまり浅すぎて意味がわかんない」
どうして嘘をついたのか彼を問い詰めはしなかった。どうせろくな理由はないはずだから。そう、深刻に考えることじゃない。浮気されたとか、詐欺だったとか、そういうことではないのだ。笑って水に流すことだってできるのだ。
嘘をつかれたことに怒っているんじゃない。私だって彼にいっぱい嘘をついている。でも彼の嘘はどうでもいい嘘で、だからどうしたと言いたくなるような嘘で、だからなおさら、彼がわからない。
彼と別れたのは日曜日の朝だった。彼が眠っている間に、枕元に置いてあったロイド眼鏡を手に取りかけてみた。なるほど、レンズではない、ただのガラスだ。どこを向いても歪みがない。ストレートに見える。ベッドから起き上がり、素裸にロイド眼鏡をかけた自分を鏡に映してみた。不思議だった。眼鏡をかけているだけで、魔術をかけたように、自分の裸身がとてもエロチックに見えた。
彼を起こさないようそっと服を着て、ホテルを出た。眼鏡をかけていない彼の顔はのっぺりとして、誰の顔でもないように見えた。私は、誰と付き合っていたのだろう。
眼鏡をかけたまま外を歩いた。日曜の早朝なので人通りは少なかったが、犬を散歩させている人がすれ違いざまにちらちら私を盗み見た。それはそう。若い女がこんなみっともない眼鏡をかけて歩いているんだもの。眼鏡越しに見る世界は、ただの伊達眼鏡なのに木の葉も空の雲も、やたらくっきりとして痛いほどに鮮やかだった。
もともと、そんなに好きじゃなかったのよ。そう自分に言い聞かせながら歩いた。なのに、長い橋を渡って地下鉄の駅に向かう途中、川を渡る風が襟から胸元に吹き込んで、肌寒さにぎゅっと襟元をすぼめた途端、心臓がきゅるると音を立て、「あれっ、あれっ」と戸惑ううちにぼろぼろ涙があふれてきた。どうして泣いているのか自分でもわからなかった。悲しいことなんかひとつもないのに。
視界が涙でにじみ眼鏡の上からハンカチでおさえた。歩けなくなって、橋の真ん中で立ち止まった。自分の体が、まるで新聞紙みたいにくしゃくしゃに丸まって、どこまでも縮んで消えてしまいそうで、わたしは悲しみという感情に取りすがって自分を守るしかなかった。