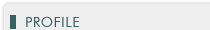志賀泉の「新明解国語辞典小説」
ろ
ロイドめがね
2012/05/01
ロイドめがね【ロイド眼鏡】
〔Lloyd=人名〕セルロイド製の太い縁をつけた眼鏡。
まんまるのレンズに黒くて武骨なセルロイドのフレーム。彼のお気に入りの眼鏡は、とっぽい。昭和の白黒映画に出てくるおじさんがかけていそうな眼鏡だ。
それもそのはず、世田谷名物のぼろ市で見つけた骨董品で、骨董品というよりがらくたで、昭和二十年代の品らしいが、古ければ価値があるというわけでもないだろう。ロイド眼鏡というそうだが、これが似合ってしまう彼もまた、とっぽい。
「永井荷風みたいだろ」と彼は言う。永井荷風という小説家がかけていた眼鏡に似ているそうで、それがつまり彼のお気に入りの理由だが、永井荷風という人自体がさほどイカしているわけではなく、もちろん荷風の時代にはダンディだったのだろうが、現代人の私から見ればとぼけたおっさんでしかない。
二千円の値札がついていたのを千円に値切ったと彼は自慢するが、私に言わせればそれでも高すぎる。こんなもの、道に落ちていたって誰も拾わない。
「買った時は度がきつくってさ。ぼろ市の人混みの中をぶつかりながら歩いて、しまいには頭がくらくらして吐きそうになった」
「無理しないで外したらよかったのに」
「いや、俺としては手に入れた時の感動を維持していたかったのよ。レンズを交換するのにメガネ屋に入るまでは意地でかけていたもんね」
ばかみたい、と私は心の中でつぶやく。ばかみたい。どうでもいいことに意地をはるのが彼の癖。生き方、と言ったら大袈裟か。もちろん上手な生き方ではない。
彼は三流大学の文学部を出ていて、いちおう夢は小説家らしく、ちょろちょろとしょぼい短編を書いている。でも書きっぱなしで新人賞に応募することはない。じゃあなんのために書くのかと聞けば「自給自足」だという。自分で読みたい小説を自分で書いて悦に入る。つまり自己完結しているわけだ。
あこがれの小説家は永井荷風。娼婦との交情を書いた小説家だ。なぜ好きかと聞いたら「洒脱」と彼は答えた。彼はとても洒脱に見えないけれど。でも飄々とした雰囲気は荷風と似ているかもしれない。
ぼろ市で彼がロイド眼鏡を手に入れた時、私は彼のそばにいなかった。彼のそばにいたのは私の知らない女の人だ。その人はロイド眼鏡をかけた彼にどんな感想を述べたのだろう。歯の浮くようなお世辞を並べてさんざんおだて上げ、どんどん木に登らせてついには下りられなくさせたのだろうか。私が知っているのは、年上で背の高い女というだけだ。色っぽくて、水商売系で、というのは私が勝手に加えた想像だ。
ぼろ市の雑踏を、度の合わない眼鏡をかけてふらつく彼の手をとり、人波を割ってずんずん歩く派手めの女を私は思い描く。別れた理由は知らない。理由がなくたって人は別れる。私が彼と出会ったのは、彼がその女と別れてしばらくしてからで、その時すでに彼はロイド眼鏡を四六時中かけている人になっていた。
どうせ永井荷風にあこがれているならレトロに徹してソフト帽でもかぶっていればまださまになっていただろうが、出会いの場面で彼がかぶっていたのは焦げ茶のニット帽で、ロイド眼鏡との相乗効果でなおさら彼をとぼけた顔に見せた。ぬうぼうとして、とらえどころのない彼に、私はつい油断してしまった。いい人かもしれないと思った。私は二年間付き合った人と別れたばかりだった。
初めて彼と寝た時、彼は裸になっても眼鏡をかけていた。シャワーを浴びた彼は、全裸に眼鏡という格好で浴室から出てきたので、先にベッドに入っていた私はびっくりした。
「はだか眼鏡」と私はからかった。「はだかエプロンってあるでしょ。あれの眼鏡バージョン。はだか眼鏡」
「はだかエプロンってしたことある?」
「ないわよ。あるわけないでしょ」
「今度してみてよ」
「いやよ。エプロンだって持ってないのに」
「眼鏡がないと正面と背中の区別もつかないんだ」
「それって、女性に対してすごく失礼」
「顔だと思ってキスしたらそれが足だったりする」
「顔がこんなことする?」
ベッドに寝そべったまま、私はつま先を跳ね上げて彼のお腹を蹴ってやった。
彼は私の脚を広げながら、ロイド眼鏡をはずしてそっと腕を伸ばし、私の顔にかけたのだった。視界が薄ぼんやりとして、それはすごくエロチックな行為に思えた。けれどそれだけに、なんだか嫌な気分が込み上げもしたのだ。彼は、前の女ともこんな戯れをしていたのだろうか、そう思うと堪らなかった。知らない女が私に乗り移ってきて、私が私でなくなっていくような気がした。声をあげても、自分の声でないような気がした。
私は特に彼を好きというわけではなく、寂しかっただけかもしれない。付き合っていればだんだん情が移っていくだろうと期待したし、実際そのとおりになりかけていたけど、心の芯は冷めていた。心の底から好きというふうにはなかなかなれなかった。それは秘密だった。でも、彼だって同じはずだと勝手に決めつけ、お互いさまだと思い込もうとした。私はずるいのかもしれない。
彼のロイド眼鏡が実は度の入っていない伊達眼鏡だと知ったのは、彼と付き合い始めて半年ほどたってからのことだ。喫茶店でたまたま出会った彼の友達が教えてくれた。
「あれ、知らなかったの?」
友達は心底意外そうな顔をして、それから空気がとても気まずくなった。なんだか、知ってはならない秘密を知ってしまったような気がした。
「だって、目が悪いって言ってたし、運転免許証の写真だって眼鏡をかけてるし。更新のときに視力検査をしたわけでしょ」
「検査で嘘をついたんだよ。徹底するからな、あいつは」
私が彼の眼鏡をかけたのは、彼と初めて寝た時の、あの一回きりで、たしかにあの時はぼやけて見えたはずだが、よくよく考えてみるとあれは、レンズが彼の息で曇っただけだったのかもしれない。
ショックだった。何者なのだ、あいつは。ほとんど意味のない、どうでもいい嘘なだけに、彼という人間がわからなくなった。このていどの嘘も見抜けなかった自分自身も信じられなかった。私はいったい彼のなにを見ていたのだろう。
「でも、伊達眼鏡ってふつうおしゃれでするものでしょう。ぜんぜんおしゃれじゃない」
「そこがあいつのひねくれ者たるゆえんだ」
「私、だまされてたのか」
「あ、いや、だましている意識はないと思うよ。たださあ、なんていうか、あいつは昔っからああいう奴なんだよ。深い意味なんてないんだよ」
「わかってる。ただ、あんまり浅すぎて意味がわかんない」
どうして嘘をついたのか彼を問い詰めはしなかった。どうせろくな理由はないはずだから。そう、深刻に考えることじゃない。浮気されたとか、詐欺だったとか、そういうことではないのだ。笑って水に流すことだってできるのだ。
嘘をつかれたことに怒っているんじゃない。私だって彼にいっぱい嘘をついている。でも彼の嘘はどうでもいい嘘で、だからどうしたと言いたくなるような嘘で、だからなおさら、彼がわからない。
彼と別れたのは日曜日の朝だった。彼が眠っている間に、枕元に置いてあったロイド眼鏡を手に取りかけてみた。なるほど、レンズではない、ただのガラスだ。どこを向いても歪みがない。ストレートに見える。ベッドから起き上がり、素裸にロイド眼鏡をかけた自分を鏡に映してみた。不思議だった。眼鏡をかけているだけで、魔術をかけたように、自分の裸身がとてもエロチックに見えた。
彼を起こさないようそっと服を着て、ホテルを出た。眼鏡をかけていない彼の顔はのっぺりとして、誰の顔でもないように見えた。私は、誰と付き合っていたのだろう。
眼鏡をかけたまま外を歩いた。日曜の早朝なので人通りは少なかったが、犬を散歩させている人がすれ違いざまにちらちら私を盗み見た。それはそう。若い女がこんなみっともない眼鏡をかけて歩いているんだもの。眼鏡越しに見る世界は、ただの伊達眼鏡なのに木の葉も空の雲も、やたらくっきりとして痛いほどに鮮やかだった。
もともと、そんなに好きじゃなかったのよ。そう自分に言い聞かせながら歩いた。なのに、長い橋を渡って地下鉄の駅に向かう途中、川を渡る風が襟から胸元に吹き込んで、肌寒さにぎゅっと襟元をすぼめた途端、心臓がきゅるると音を立て、「あれっ、あれっ」と戸惑ううちにぼろぼろ涙があふれてきた。どうして泣いているのか自分でもわからなかった。悲しいことなんかひとつもないのに。
視界が涙でにじみ眼鏡の上からハンカチでおさえた。歩けなくなって、橋の真ん中で立ち止まった。自分の体が、まるで新聞紙みたいにくしゃくしゃに丸まって、どこまでも縮んで消えてしまいそうで、わたしは悲しみという感情に取りすがって自分を守るしかなかった。