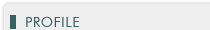志賀泉の「新明解国語辞典小説」
ら
らんちゅう
2012/01/24
らんちゅう【蘭虫】
キンギョの一種。からだは球形にふくらんでいて、背びれが無い。まるこ。
体の弱い弟のためにお父さんが買ってきたキンギョは一匹一万円近くした。
らんちゅう。
「これでも安い方なんだよ」お父さんは弁解がましく言う。少し悪びれながら。「十万円以上するものだってざらにあるんだから」
わたしはたぶん、膨れっ面をしていたのだと思う。だってわたしは、靴屋の店先でねだった一足三千円のサンダルを「高すぎる」という理由で却下されたばかりだったのだ。
らんちゅう。
どこが可愛いのかわからない。お腹がやけに膨れてずんぐりむっくり。背びれがなくて不器用そうなよたよた泳ぎ。そしてそう、顔。瘤だらけの不細工な顔。うろこだけは、見事なくらい紅いのだけれど。
グロテスク。そう思った。なのに見る人が見れば、この瘤が愛らしいのだという。顔がでこぼこなほど値打ちがあるそうだ。人の価値観ってさまざまだ。
弟はらんちゅうのどこが気に入ったのだろう。弟は動物が好きで、けれどアレルギー体質だからペットは飼えなくて、だから近所のホームセンターに家族で買い物に行く時は必ずペットコーナーに寄ってガラス越しに犬や猫を見せてあげるのだが、ある日、弟はひとつの水槽の前で釘付けになって、何を熱心に覗いているのかと見てみれば、やけに丸っこい赤いのがひらひら泳いでいて、それがらんちゅうなのだった。
「キンギョが好きなの?」と訊ねてみても、返事は「アー」か「ウー」。
弟は口がきけない。弟は十三歳だが三歳か四歳くらいの知能しかない。体も不自由で生まれてこのかた自分の足で立ったことがない。どのくらい言葉を理解しているのかわからないけれど話をするのは好きで、わたしがお父さんやお母さんと話をしていると「アー」とか「ウー」とか割って入る。邪魔をする。お父さんやお母さんをわたしに取られると心配になるのだ。弟は独占欲が強い。わたしの会話は中断されて、お父さんもお母さんも弟にかかりきりになる。わたしは放っておかれる。
「カッちゃんは長生きできないのだから」さんざんそう聞かされてきた。克己というのが弟の名前だ。「なるべくよくしてあげないと」
そう、弟のおかげでわたしは我慢強い子に育った。長くは生きられなのだからと、ずいぶん弟の面倒をみてきた。誰からも感謝されずに。でも頭の片隅ではこうも思っていた。
ひょっとして、弟は死なないのではないか。
もちろん、弟が早く死ねばいいと願っているわけではない。けれど、自分を犠牲にして弟に尽くす日がこの先何年も続くのかと思うとぞっとする。心が暗くなってしまう。わたしは冷たいのかもしれない。でも、わたしの人生はわたしのものなのだ。わたしだって、誰にも邪魔されずにわたしの人生を生きたいのだ。
お父さんがらんちゅうを買ってきた時も、わたしはうんざりした。なぜって、らんちゅうの世話をするのはわたしに決まっているからだ。
お父さんは大きな水槽も買ってきていた。水槽に砂利を敷いて、水を入れて、ぷくぷく泡の出る装置を仕込んだら、案の定、「じゃあこれを読んでおいてね」とお父さんはわたしに『らんちゅうの飼い方』という本を渡したのだ。お姉さんなのだから当たり前だろう、というように。わたしはうんざりを通り越して、なんだか悲しかった。でも悲しいなんて誰にも言えない。おくびにも出せないのだ。
らんちゅうは品種改良によって作られた生き物で、存在そのものが不自然だから、当然のことながら体が弱く、水温の管理とかエサの与え方とか神経を使う。世話がやけるのは弟と同じだ。夏休み前、予想に反して気温がぐんぐん高くなっていく日があり、わたしは部屋のカーテンを閉め忘れてきたような気がして、もし閉め忘れたのなら部屋の温度もぐんぐん高くなって水温が上昇しらんちゅうは死んでしまうのだが、お父さんもお母さんも働いているから確かめることができず、心配で心配で先生の声がちっとも頭に入らなくなり、昼休みに友だちの自転車を借りて家に帰ってみたら、部屋のカーテンはちゃんと閉まっていた。汗だくになって自転車を飛ばした自分がばかみたいだった。
放課後は、養護学校に寄って弟を引き取り、車椅子を押して家に帰る。おかげでわたしは部活動だってできないのだ。感心ですねって大人には褒められる。褒められるとうれしい。でも小学校の時はクラスの男子によくからかわれた。「アー」とか「ウー」しか言えない弟はみっともない。元気な弟のいる友だちがうらやましかった。できたら交換したかった。「おねえちゃん」とスカートの裾を引っ張られながら弟と散歩してみたかった。わたしは弟にいろんなことを教えてあげられたのに。どうして雨は降るのかや、どうして虹ができるのかを。
家に帰れば、キンギョ一匹には大きすぎる水槽を、らんちゅうは深紅の尾びれをひらひらさせて気ままに泳いでいる。わたしの苦労なんて知るよしもない。知るわけがない。瘤の谷間に埋もれたちっちゃな黒い目は、赤ん坊みたいに無垢だ。
死んでたらよかったのに。わたしはらんちゅうを恨んだ。死んだらよかったのに。
弟は水槽の横に車椅子を寄せて、指先を水面に差し込む。らんちゅうはエサをもらえると勘違いし、ふらふら寄ってきては口をぱくぱくさせる。弟はそれがうれしいのだ。何度でも同じことを繰り返す。らんちゅうもまた、何度でもだまされるのだ。似た者同士、とひそかに思う。似た者同士。
カーテンを開くと西の雲が夕陽に紅く染まっていた。まるでキンギョのうろこみたいな紅蓮の空だった。
『らんちゅうの飼い方』によれば、らんちゅうを作ったのは江戸時代の日本人なのだそうだ。たぶん、物好きな江戸人が、たまたま変な形に生まれたキンギョを、もっと変わった形にしてやろうと、似たようなキンギョと掛け合わせて、どんどん変な形にしていって、それを「らんちゅう」と名づけたのだ。「らんちゅう」が世に出回ると、変な形を競うようになり、いつの間にか変な形ほど「可愛い」ということになった。きっとそういうことなのだろう。
らんちゅうは自分をどう思っているのだろう。不格好で、醜くて、泳ぎも下手で、本来ならマイナスでしかない性質を逆に愛でられるなんて、自分が悲しくはならないのだろうか。
らんちゅうが死んだのは夏の終わりだった。
深夜のこと。お隣の家が火事になった。お隣は中華料理屋さんで、その厨房から火が出たのだった。ドンッという何かが爆発するような音に飛び起きたら、窓ガラスはもうお隣の炎に赤々と染まっていたのだ。
パジャマのまま階段を駆け下りたら、お父さんは消火器を手に、爆風で割れた廊下の窓から外へ向けて消火剤を吹きかけていたが、そんなもの役に立たないくらい見ればわかりそうなものだった。
弟の部屋ではお母さんが弟を叩き起こしていた。寝ぼけている弟を車椅子に乗せるのをわたしも手伝った。こんな時だからこそ実感してしまうのだけれど、弟は重い。思春期に入って食欲が増し、腰がひとまわり太くなった。おまけに半分眠っているから抱きかかえるだけでもひと苦労だった。
弟を車椅子に移すとお母さんは現金や預金通帳や土地の権利証や、大事な物を取りに寝室へ戻り、わたしは弟の体に毛布をかけてやりながら、ちらっと水槽に目をやった。らんちゅうは淡い光の中に沈んで眠っていた。わたしはそのまま車椅子を押して玄関に向かった。
弟と家の外に出ると、道ばたにはもう野次馬が集まっていた。わたしは自分の洋服や教科書を取りに家へ戻ろうとして、みんなに引き止められた。その頃には、火はわたしの家に燃え移っていたのだ。
日常って、こんなに簡単に壊れるものなんだ。否応なしに奪われていって、もう取り返しようがないんだ。わたしは茫然と突っ立って、燃えていく我が家を見ているしかなかった。
でも、わたしが大切にしている洋服や教科書やアルバムなんかを、お父さんは両手に抱えて運んできてくれた。泣きたいくらいうれしかった。お母さんも大きなバッグを提げて出てきた。不幸中の幸いというか、お隣さんもふくめて全員無事だった。
ただし、らんちゅうを除いて。
「らんちゅうは?」わたしは訊ねた。
お父さんは、はっと思い出したような顔になり、「仕方ないさ、あきらめよう」とため息を吐いた。お父さんはらんちゅうのことをすっかり忘れていた。
わたしは気づいていた。なのに見捨てた。その気になれば助けられたのに、時間の余裕はあったのに、どうして見殺しにしたのだろう。自責の思いに、心臓がぎゅっと押し潰された。涙があふれてきたが、誰にも涙の理由を言えなかった。
そうしているうちにも火は燃え広がり、消防車のサイレンの音は遠くから聞こえるのだけれど、どこでつかえているのか、なかなか近づいてくる様子がない。
ようやく到着した消防隊が消火作業を始めても、火の勢いは止まらなかった。すっかり目覚めた弟は興奮してやたら叫び続けた。
屋根が崩れ、ぽっかり開いた穴からひときわ高く火柱が立ち上がり、夜空を焦がした。
その時、わたしは見たのだ。舞い上がる火の粉のただ中から、巨大ならんちゅうが現れるのを。顔の瘤が炎を浴びて紅蓮に輝き、緋色のうろこが火の粉を振り払い、らんちゅうは悠然と尾びれを振りながら、天空を泳いでいった。
幻覚だろうか。もし幻覚だとしても、同じ幻覚を弟も見ていたのだ。
弟は車椅子から身を乗り出し、炎に顔を赤く染め、まるでらんちゅうみたいな顔で、しきりに口をぱくぱくさせながら夜空を見上げていた。
声にはならなかったけれど、その口の形がわたしには、俺も連れて行ってくれと、訴えているように見えたのだった。