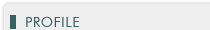志賀泉の「新明解国語辞典小説」
わ
わたつみ
2012/07/09
わたつみ
〔「わた」は海、「つ」は「の」に当たる雅語の助詞、「み」は神の意〕海(を支配する神)。
「俺たちはみんな海の神の子孫なのさ」
そう言い切った君の強さはどこから来るのだろう。
アイルランドで漁師になりたいと君は言ったね。なぜアイルランドなのかは聞かなかったよ。いつもの大風呂敷だとばかり思っていたからさ。
だから君が銀行員をやめて漁師に転職したと聞いたときは本当にぶっとんだ。足が頭の上まで上がっちまったくらいだ。しかもアイルランドの寒さに慣れるんだとかで、東北の漁師に弟子入りしたんだから。おいおい、計画性と無謀さが背中合わせでダンスを踊ってるぜ。僕には「肝心なのは人生設計」とか言って預金通帳を作らせたくせに。
ところで君はアランセーターの伝説って知っているかい。アイルランドのアラン島のご婦人たちは、旦那が海に落ちて死んでも網目模様で身元がわかるようにって、手編みのセーターを旦那に着せて荒海に送り出したそうだ。まあ、これはあくまでも伝説であって事実ではないそうだが、それだけ漁師の仕事は死と隣り合わせってことだ。板子一枚下は地獄って、君も聞いたことはあるだろう。
「また見つかった。なにがって、永遠さ、海と溶け合う太陽さ」
東京の青山にあるアイリッシュ酒場で、ギネスビール片手に床を踏み鳴らしながら君はランボオの詩の一節を諳(そら)んじてみせたね。そういうきざったらしさが、君の憎らしさであり、同時に魅力でもあったのだけど。
去年の冬、洋子さんと僕とで君に会いに行ったことは憶えているだろう。あの日は海が荒れて漁は休みで、君は僕らを連れて行きつけの居酒屋に入り、地元でどぶ鍋と呼ぶアンコウ鍋をごちそうしてくれた。洋子さんはこういう店は初めてだっておどおどしていた。風が吹くと窓ががたがた鳴り、石油ストーブの上でヤカンがしゅうしゅう湯気を立てているような店は。それより驚いたのは君の変貌ぶりだ。余分な肉が削げて顔が引き締まり、目は精悍そのもの、無精ひげも様になって、すっかり狩猟民族だ。これが君の真の姿で、都会の銀行員だった君は仮の姿だったんじゃないかと思ったくらい。でもそれは君の適応能力の凄さであって、違和感のない東北弁を使って地元の人と冗談を交わしている君を見てると、アイルランドで漁師を始めてもきっとこんなふうにうまくやれるんだろうなと感心したものさ。
居酒屋を出て、火照った頬に刺すような北風を受けながら路地を抜けて港に出ると、のっぺりと暗い海面が上下に波打ち、接岸された漁船同士が揺れてぶつかりごんごんと鈍い音を立てるのを、洋子さんは「船のおしゃべり」と言った。君はわざわざ自分が乗っている漁船のところまで僕らを案内してくれたけど、はっきり言って迷惑だったよ。自分の吐く息があんなに冴え冴えとして見えたのは生まれて初めてだ。水銀灯の光に浮かび上がる白い船体が、吹きつける寒風に凍えて夜空に吠えているようで、「タラ漁はいまが最盛期で」なんて君の解説はちっとも耳に入らなかった。
海はどこまでも暗く、堤防に寄せては砕け散る波飛沫がしらじらと浮かんで、僕も洋子さんもそれがなんだか怖ろしくて、がたがた震えながら目を奪われていた。けれどその横で君は、自分の未来にばかり目を奪われていたんだよな。
そうさ、君は勇敢で、自由で、楽天家で、いつだって前を向いている。なあおい、君はあのとき、暗い海の向こうになにを見ていたんだい。
さっさと日本を離れてアイルランドに行っちまえばよかったものを。そうすりゃ津波なんかに巻き込まれずにすんだのに。
あの日、洋子さんが君にプレゼントしたアランセーターが、伝説どおりに身元確認の手掛かりになるなんて、悪い冗談だよ。セーターそのものは既製品だけど、洋子さんがその上から君のイニシャルを編み込んでいたんだってな。洋子さんは自分を責めていたよ。私がよけいなことをしたから死神を呼んだんだって。あの津波じゃあ、死神の出る幕もなかったと思うけどな。
あんなひどい死に方ってない、と洋子さんは泣いた。七日もたってから引き揚げられた車の中に君はいたんだ。どんな状態だったかは想像がつくだろう。
洋子さんは君の恋人ということで、君の両親から形見の品としてアランセーターを分けてもらい東京に持って帰った。何度となく漂白剤に漬けては干してを繰り返し、毛糸をほどいて編み直し、ふたつの毛糸帽に生まれ変わらせた。そのひとつを彼女がかぶり、もうひとつは僕がもらった。
ほら、見えるか。僕がいまかぶっている、この毛糸帽がそうさ。発見されたときに君が着ていた、あのセーターの毛糸で編んだんだ。結び目がところどころにあるのは、セーターが破れていたからさ。乳白色の生糸を染めている染みは、洗い落とせなかった君の体液だ。人が聞いたら気味悪いとかグロテスクとか陰口を叩くかもしれないけど、僕はそう思わない。毛糸帽をかぶっていると君を身近に感じる。君が死んだとは思えない。だって、死んだ人間に温もりはないはずだもの。
正直に言うと、僕はひどく落ち込んでなかなか立ち直れなかった。いや、悲しんでいるうちはまだよかったんだ。悲しみが抜け落ちた後の虚脱感のほうがひどかった。朝、目覚めるとなんにもしないうちから体が疲れ果てていた。毎日がそんなふうに始まった。電車に乗ってもどこかに寄りかかっていないと立っていられない。あれはしんどかったよ。いっそ病気になったほうが楽だと思ったくらいだ。
でも考えてみれば洋子さんのほうが僕の数倍は辛かったはずで、その洋子さんが僕に毛糸帽を渡して「海を見に行こう」と誘ってくれたときは、僕は洋子さんの強さに怖れをなしたものさ。
津波から半年が過ぎて、いまは夏の終わりで、君のいた街は津波に根こそぎさらわれてそっくり消えてなくなり、青草がぼうぼうに伸びてモンゴルの平原みたいだった。僕らは目を疑ったよ。モンゴルと違うところは漁船がごろごろと転がって遠くに水平線が見えることだ。君が住んでいたアパートも、どぶ鍋をつついた居酒屋も、どこにあったのやら、こうなってみるとさっぱり見当がつかない。ただ、以前は人の家の庭だったと思しきところにコスモスやらケイトウやらがまとまって咲いているのが、わずかに心を和ませてくれたけど。
堤防に立つと信じられないくらい海は穏やかで、打ち寄せてくる波を見ていると空っぽになった心になにかが満たされてくる思いがする。
なあ、そっちから僕らはどんなふうに見える? 季節はずれの毛糸帽をかぶった男女が堤防の上で肩を並べているというのは。
僕は毛糸帽を脱いで鼻にあてがう。深く息を吸いこむとかすかに異臭がする。それは、漂白剤でも消せなかった君の死臭だそうだが、生も死もあるもんか、君の体から染み出てきたものなら、それはやっぱり君の臭いだ。
なあ、君はどこにいるんだよ。僕はもしかすると、君よりも深く死んでいるんだ。
「また見つかった。なにがって、永遠さ、海と溶け合う太陽さ」
洋子さんは遠い目をして、墓碑銘を読むようにつぶやいた。
おい、永遠は見つかったか。ていうか、君が永遠そのものになっちまったんだよな。