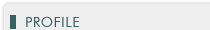志賀泉の「新明解国語辞典小説」
わ
わなわな
2012/07/09
わなわな
恐怖などのためにからだが小刻みに震える様子。
まあ、想像してほしい。朝、着替えようとしてタンスを開けたら、吊り下げた洋服の間で見知らぬ女の子がうずくまっていたとしたら、どんなに驚くか。
あり得ない? でも現実にそれは起きた。どんなに妙なことでも、起きたことは起きたこととして、冷静にこれを受け入れなければならない。
彼女は二十歳前後、髪が長く、水色のワンピースを着て、肌の色もワンピースに似て青白い。よく見れば剥き出しの肩が小刻みに震えていた。
どこから入ってきたのか。どんなに記憶をひっくり返しても部屋に招き入れた覚えはない。酔っぱらって連れ込んでおいて忘れたとも考えにくい。昨夜はしらふで帰ってきたのだ。かといって泥棒にも見えない。だいいち僕のマンションはセキュリティが万全で、そうやすやすと侵入を許すシステムではない。
「もしもし」僕は声をかけた。「もしもし、そこでなにをしているのですか」
いくら怪しくても相手は女の子だ。乱暴には扱えない。
「すいません、追われているのです。かくまってくれませんか」
かすれた声で彼女は懇願した。その声が真に迫っていたので、念のため僕は部屋の中をぐるりと見渡した。
「特に変わった様子はないけど」
「タンスの中に置いてもらえればいいのです」
「まいったなあ」僕は鼻の頭をぽりぽり掻いた。「かまわないけど、僕はこれから着替えて会社に行かなくちゃならないんだ。ちょっとどいてもらえないかな」
「あ、すいません」
彼女は膝をぎゅっと抱えて小さくなった。折りたたみ椅子をたたむように、膝を抱えた彼女はちょっと信じられないくらい薄くなった。
それで僕はワイシャツとネクタイとスーツを取り出し着替えることができたのだが、その間も彼女は肩を震わせていた。
彼女はなにに怯えているのだろう。君は誰で、誰に追われていて、どうやってこの部屋に入ったのか、いくら尋ねても答えてくれない。しかし、だからといって無下に追い出すわけにもいかない。僕のせいで彼女が殺された、なんてことになったら嫌だもの。
「じゃあ、僕は出かけるけど、誰かに押し込まれそうになったら玄関横に防犯スイッチがあるからそれを押すといい。三十分以内に屈強な警備員が駆けつけてくれるはずだ」
侵入者に防犯システムを説明するのもおかしな話だが、成り行き上やむを得ない。
僕はタンスの扉を閉めた。「ありがとうございます」とか細い声が聞こえた。
会社の同僚に今朝の出来事を話すと、同僚は「ああ、それは妖怪わなわなさんだね」と、なんでもなさそうに言った。
「妖怪わなわなさん?」
「座敷わらしみたいなもんさ。気にしなさんな」
「しかし、いくら妖怪とはいえ洋服ダンスに女の子がいるのは落ち着かないな」
「その女の子に見覚えはないの?」
「ないよ」
「ほんとに?」
「ほんとにないったら」
「それはどうかな。忘れているだけかもしれないぞ」
同僚は含み笑いを浮かべた。僕は軽く腹を立てた。だいたい、彼女はやせっぽちで、いかにも貧相で、ぜんぜん僕の好みでないのだ。
「彼女はなにに怯えているのだろう」
「それは愚問というものだ。妖怪あずき洗いにどうしてあずきを洗っているのか尋ねるようなものだ」
同僚が言うには、わなわなさんは無害な妖怪で、福を呼びもしないかわり災いをもたらしもしない。放っておけばいつの間にかいなくなるということだった。
夕方、帰ってみると部屋に異常はなかった。玄関にもリビングにも荒らされた形跡はない。ほっとしながらタンスを開けてみると、中にはやはり、女の子がうずくまってわなわな震えていた。彼女はどこから見ても生身の人間で、とても妖怪には見えない。
「ずっとそこにいたの?」
普段着に着替えながら彼女に話しかけた。彼女はこっくりうなずいた。僕はそっと彼女の顔を盗み見た。やっぱり見覚えはない。
スーツをタンスにしまおうとすると、彼女はぎゅっと膝を抱き寄せ体を折りたたんだ。妖怪なりに遠慮しているらしい。
「誰も押し入ってはこなかったんだ」
「はい、おかげさまで」
「じゃあそこから出てきてもいいんじゃないかな」
「いえ、まだ安心はできません」
「気が進まないなら、僕も無理には引っ張り出さないけど」
「ありがとうございます」
たしかに無害そうではある。
僕は台所で料理を作り、テレビニュースを見ながら食事をし、ビールを飲み飲み借りてきた映画のDVDを見ていたが、その間タンスの中からはことりとも音がしなかった。もう消えてしまったのだろうか。気になって扉を開けてみたら、まだいた。膝頭にのせていた額を起こし、「お出かけですか?」と、膝を抱き寄せた。
「あ、いや、僕はもう寝るからね。おやすみを言おうと思って」
「あ、はい」
「なんならソファで寝てもかまわないけど」
「いえ、油断はできませんから」
彼女は細長い指で自分の肩を抱き、わなわな震えた。扉を閉めてタンスに背を向けてから、「おやすみなさい」と消え入りそうな声が聞こえた。
その夜はなかなか寝つけなかった。「見覚えはないの?」という同僚の言葉が気にかかり、中学時代から今日までの、僕が付き合った、あるいは付き合ったとは言えない、遊びで終わった女性や一夜限りの女性も含めて片っ端から思い出してみた。どの顔も彼女に似ていなかった。しかしそれは同時に、どの顔も彼女に似ているとも言えた。
ふと、人の気配がして目を開けた。彼女が金属バットを振りかぶり枕元に立っていた。「え?」と声を上げる間もなく、金属バットが顔面めがけて振り下ろされる。僕は咄嗟にかわしてベッドから転げ落ちた。彼女の金属バッドが執拗に僕を追った。ワイングラスが割れ、ステレオ装置が砕け、目覚まし時計がはじけ飛んだ。「おい、ちょっと、待て、君は無害のはずだろ」抗議をしようにも声が出ない。僕は転げ回り、逃げ惑い、寝室の角に追い詰められた。彼女の金属バッドがうなりを上げる。僕は頭を抱えてうずくまる。頭蓋骨に鈍い衝撃を覚えた。次の瞬間、目が覚めた。
夢だった。僕はベッドの上にいた。寝室はしんと静まり返っていた。
翌朝、タンスを開けてみると彼女は吊り下がった洋服の間できちんと膝をそろえて正座していた。
「ありがとうございました。もう大丈夫です」
彼女は深々と頭を下げた。
「ああ。それはよかったですね」
よかったとしか言えない。昨夜の夢のことは黙っていた。
「たいへんご迷惑をおかけしました。ご親切は忘れません」
彼女はタンスから足を下ろし、ゆっくりと背筋を伸ばして玄関に向かい、いつの間にか手にしていたハンドバッグからハイヒールを取り出し足にはめると、妖怪らしからぬ礼儀正しさでもう一度深々とおじぎをし、ドアの外へ去っていった。
リビングに戻ると、いつの間にかテーブルの上にスルメが置いてあった。お礼のつもりだろうか。