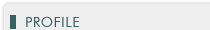志賀泉の「新明解国語辞典小説」
ら
ライフサイクル
2012/01/24
ライフサイクル【life cycle】
①動物の個体が発生してから死ぬまでの過程の称。②その物が売れ始めてから商品としての寿命が尽きるまでの期間。③結婚に始まり、家族の発展・自己の死亡に至るまでの長期展望。
たまには自分のことをたらたら書いてみようと思う。面白いか退屈かは抜きにして。
ライフサイクル?
そう、これから僕はライフサイクルについて書かなくちゃならない。
ご存知のとおり、この短編連作は「新明解国語辞典」から適当な言葉を選び、その言葉をタイトルにして小説を書いている。「ら」の段の場合、まず「雷火」「落雁」「ラバーソール」「ラム」「ランドマーク」を候補に選んだ。語感がいいのと、なんとなくイメージが膨らみそうな言葉だからだ。
たとえば「ラバーソール」。(厚い)ゴム底の靴のことだが、舌の上で弾むような語感がいい。ラバーソール。口ずさむだけで心が浮き立つ。ソール(靴底)はソウル(魂)にも通ずる。しかしストーリーがまるで浮かばない。却下。
「落雁」もいい。渡りの途中で力尽きた雁が、群から離れて荒野に落ちていく、月夜の情景が目に浮かぶ。侘び寂びが効いていて、しかも鮮烈。井上陽水の『神無月にかこまれて』という曲が頭にあった。そこからイメージが膨らみそうな予感がしたが、どうひねっても思わせぶりなストーリーにしかならず、これも却下。
ひとつひとつ却下していき、結局すべて却下すると、もう一度「新明解国語辞典」を開くことになる。面倒がっていたら作家なんてやっていられない。
そうして拾い上げた言葉が「ライフサイクル」。生まれてから死ぬまでのこと。
ライフサイクル。ライフサイクルに関する記憶を探っていく。
以前、ドトールでコーヒーを飲んでいたら、隣のテーブルから「決めた。これは私の走馬灯に入れる」と女の子の声が聞こえてきて、びっくりしたことがある。
人は死ぬ間際に、一生分の記憶を走馬灯のように見るというが、彼女の場合、なるべく気持ちよく死ねるようにと、今の内から走馬灯に入れる記憶と外す記憶を分けているという。ちょうど、ケータイのメール記録を保存したり消去したりするのと同じ感覚か。
盗み聞きしながら、へえ、と感心した。なるほど、うまくいけばポジティブに死ねそうな。できることなら僕だって、嫌な思い出がぐるぐるめぐる中で果てたくはない。
それと、思い出したのはクリムトの「愛」という絵。大学の友人が美術館の売店で買った印刷物だが、部屋に飾ったら毎晩悪い夢ばかり見るので外したという。「志賀にやるよ」と言うのでもらって帰った。当時の僕はものすごく貧乏だったのだ。
若い男が女を抱きよせている、映画のポスターみたいな絵だ。二人の頭上には、女性の一生が少女、熟女、老婆の順におぼろげに浮かび、それが古いタイプの心霊写真みたいでなんとも薄気味悪い。特に老婆の怨みがましい面相はなんとも凄惨で、おぞましさに寒気が走った。
抱擁の刹那に女性の一生が浮かび上がる。一生の時間が、抱擁の刹那に凝縮される。暗示された死の影が、抱擁の場面をより生々しく艶やかに見せるのだ。
物は試し、四畳半の部屋に飾ってみた。やはり深層心理に作用するのか、その夜さっそく強烈な金縛りにあった。僕は自己暗示にかかりやすいタイプなのだ。それから毎晩、日課のように欠かさず金縛りにあったのだった。根負けして絵を捨てるまで。
未来の記憶を思い出す、ということはあるのだろうか。
小学校一年か二年のころ、死の不安にとらわれたことがある。遠い親戚の誰かが亡くなったせいかもしれない。僕は葬儀に参列しなかったが、遺体を見たという兄が「鼻の穴に綿を詰められていた」と自慢気に話していた。
兄の話から僕が想像した光景は、いつかしら僕の脳裏に定着し、今でも僕は、薄暗い座敷に眠る、鼻の穴に綿を詰められた老婆の姿を、あたかも自分の記憶であるかのようにありありと思い出すことができる。
それが、人の死というものが切実に我が身に迫ってきた最初の体験だったと思う。
死が怖くなった。死とは、この世界から自分がいなくなることなのだ。
人の中には「死の種」が生まれつき備わっている。その種が、病気をするたびに毒を吸って大きくなり、最後は宿命的にその人の生命を奪う。それが、僕が考えていた死のメカニズムだった。だから、死を遠ざけるためには病気をしなければいい。病気を予防するには日頃から薬を飲んでおけばいい。そう、僕は結論づけた。
親の目を盗み、家の薬箱から常備薬を引っ張り出してはこっそり飲んだ。薬箱は戸棚の最上段にあったが、踏み台を使えばなんとか手が届く。どの薬と決めず、手に触れた薬ならどれでもよかった。今考えるとぞっとするが、それで気分が悪くなったとか、体調を崩したとか、そういうことはなかったようだ。
ある日のこと、家の庭でひとり遊びをしていた僕は、不意に直感した。ある種の啓示が天から降りてきたみたいに。僕はひとり遊びを中断し、一歩、二歩、三歩と大股で歩き、立ち止まった。すっと気が遠くなり、目の前が暗くなって、年老いた自分の姿が脳裏に浮かび上がってきたのだった。
それですっかり安心したように記憶している。
時間は流れていない。その時、僕が直感したのはそういうことだ。時間が流れるというのは、人がそう思うから流れるのであって、本当は流れていない。過去も現在も未来も同時にある。今この瞬間に、一生分の時間が含まれてあるのだ。なんだか仏教の時間論みたいな話だが、足を止めたら自分の未来が見えてきたというのは、そういうことだ。現在の一瞬に過去も未来もあるのなら、自分の死を心配する理由なんてない。だって、それはもう今ここにあるのだから。
年老いた僕は禿げていた。着流しのかっこうで、日の当たる縁側に腰かけていた。膝には猫。僕の隣には女房らしい老婆が穏やかな笑みを浮かべている。セピア色の、古いスナップ写真みたいな情景。遠い未来でありながら懐かしさを誘うような、幸福に充ちた老後の一場面。
つまりそれは、子供心に考えた幸福な老後の一典型に過ぎず、僕が自分の未来を垣間見たとは毛ほども信じない。信じないのだけれども、心の奥にこの情景をしまっておくことで、僕はずいぶん救われた気がする。人生山あり谷ありだけれども、最後には日の当たる縁側に行き着くのだという、漠然とした安心感があったのだ。
たとえば三十五の歳に大病をわずらって手術を受けた時も、ひょっとしてこれまでかと不安になる一方で、日の当たる縁側を思い出し、まあ七十八十くらいまでは生きるだろうなと、高を括ってもいたのだ。
実際、生き延びている。あれから重い病気にかかったことはない。取りあえず元気だ。あきらめかけていた結婚も四十をすぎてから実現した。条件は整いつつある。
しかし困ったことが起きた。あの縁側だ。あの縁側は実家の縁側なのだが、古い家を取り壊して新築してしまった。しかし縁側っぽいものは付いているのでそれで代用しよう。猫はなんとでもなる。
ところが、今年になって原発事故が起き、実家に帰れなくなってしまった。僕の家は福島第一原発から20キロ圏内にある。警戒区域にすっぽり入っているのだ。
弱ったことになってしまった。警戒がいつ解除されるのか誰にもわからない。一年先になるのか数十年先になるのか。しかし永久ということはないだろう。僕が年老いるころには、原発事故は忌まわしい記憶であると同時に貴重な教訓になっているはずだ。そう信じている。
日の当たる縁側に猫を抱いて腰かけよう。女房を連れて。穏やかな心持ちでいろんなことを思い出そう。その時、僕の目は、大股歩きで一歩、二歩、三歩と庭を歩いている、幼い自分を見るかもしれない。