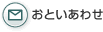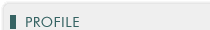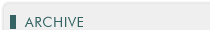谷隆一の「僕だってこんな本を読んできたけど…」
『ブブセラ――90分でわかる南アフリカ&ワールドカップ』熊崎敬/金丸知好/楠瀬佳子=文。岸本勉=写真
10/06/20
南アフリカを知る絶好の機会。
一読しておくと、W杯がより楽しめる。
意外(?)な日本チームの頑張りもあって、盛り上がってますね、ワールドカップ。
でも、改めて思うに、南アフリカのことって、ぜんぜん知りません。あんまりテレビでも、南アフリカの町並みとか歴史とかって、紹介されてない気がするんですが......。
そんな中でお勧めしたいのが、第三書館が出したこの本。サッカーの試合時間にちなんで90項目に分け、南アフリカに関しての素朴な疑問を取り上げていきます。著者たちは、現地で取材経験のあるサッカージャーナリストや、南アフリカに詳しい学者さん。気軽に読める内容なんですが、結構「へぇ~」がありますよ。
例えば、日本チームが宿泊するジョージのホテルは、宮里藍らで構成した女子ゴルフチームが「第1回女子W杯」時に泊まり、優勝を果たしたという縁起のいい場所ということ。また、南アフリカでのサッカーワールドカップは実は2回目で、2006年に、ホームレスの選手たちによる4人制サッカー大会が開かれているということ。アパルトヘイトの時代、日本人は「名誉白人」という特権が与えられていたこと。南アフリカは演劇が盛んということ。ギネスブック公認の世界一豪華な列車が走っていること......。
どうです? 知らないことがたくさんありませんか?
さらっと一読するだけで、南アフリカへの認識がずいぶん変わりました。危ない危ないと負の側面ばかり強調されますが、当たり前ですけどそこに人が住んで いるのですから。あまり接することのない国だからこそ、こんな機会に、ちょっと興味を持ってみたいものですよね
『1Q84』 村上春樹
10/05/16
残ったのは戸惑い……
中身もそうだが、売り方に注文つけたい
長らく更新をさぼっていました。半年もさぼると、どのタイミングで再開すればいいのか困惑するものですが、こんなとき、ベストセラー本はありがたいですね。
で、ご多分に漏れず、村上春樹さんの『1Q84』(新潮社)を。
率直にぼくは、とてもネガティブな読後感を持っています。断っておきますが、ぼくは春樹ファンだし、15年くらい前によくあった論争で、「村上といえば、龍か春樹か」というときには、迷わず「とうぜん春樹でしょ」と主張していました。
しかし、いま同じことを聞かれたら、どう答えるかな。龍は進歩し続けている感じがしますが、春樹はうーん......。
なんて、ぼくが偉そうに言うのも何なんですけど。
『1Q84』ですが、きっと、話にスムーズに入っていければ、大傑作なんでしょうね。実際、幾つかの評論やWEBのレビューを見ていると、そんな感じだし。
でもぼくは、物語に入っていけませんでした。まず、10歳のときの、しかも一瞬とも言うべき出会いが人生を決定していることに冷めてしまうし、感嘆せざるを得ない素晴らしい比喩表現も連発されると冷めてしまうし、何より、必要とは思えない性愛表現の続出に冷めてしまったんです。
冷めてばっかりです。マジで。
読者として期待するのは、(ノーベル賞候補ウンヌンという意味も含めて)日本で最高というべき作家の集大成作品なわけです。でも、これが集大成なのでしょうか? それにしては、未解決な点が多すぎるし、一方で人生の矛盾というか不合理というか、端的に言って、心に残るものがない。主張したいこともよく分からない(少なくともぼくには)。
で、懸念するのは、「これが文学なんだ!」と妄信する若い作家志望者が出てくることです。
特に、延々と性描写を続けることとか、ぼくには醜いこととしか思えないんだけど(もちろん必要な箇所はある)、「エロスを描き切ることこそ文学」「真相心理を性嗜好からあぶり出す」みたいな風潮が起こることをすごく心配します。若いうちは、いろいろ影響受けやすいですしね。
ところで、ぼくがこの作品をネガティブに感じているのには、内容とは別の問題もあります。
売り方です。
いまBOOK3まで終わっているわけですが、幾つかの書評などでは、BOOK4あるいはBOOK0の発行が示唆されています。BOOK3自体、BOOK2が出て少ししてから発行が発表されたわけですが、そういう小出しにする姿勢に、ぼく自身は不快感があります。だって、書き下ろしでしょ? 小出しにすることに何の意味があるのでしょうか? 最初から「1~4まで出ます」と言ったほうが親切です。
問題なのは、「BOOK3で終わりなのか終わりでないのか分からない」という今日この時点でのこの状態が、読者にとってとても不快なことだ、ということです(少なくともぼくは)。終わりか終わりじゃないか分からないというこの気持ちを、どう整理すればいいのでしょう? ここで納得するべきなのか、あるいは続きを待っていいものなのか?
こういう売り方って、不道徳なことだと思いませんか??
まあ、そうは言っても、次が出れば、やっぱり買ってしまうのだろうけど。
それにしてもぼくは、10歳のときの同級生に誰がいたのか、ただの一人も名前を思い出せません。それなりに、幸福な小学校生活を送っていたと思うのだけど。
いや、幸福だったから、何も覚えていないのかな?
『不動心――坂本博之』 加茂佳子 企画・構成
09/12/03
殺気で倒す! なんて、もう流行らないの?
ああ、懐かしき名ボクサーたち
「俺は、たとえ試合の後半まで大差のポイントで勝っていても、安全運転をして勝ち逃げしようとしたり、逆転を恐れて、倒せるチャンスを放棄するようなマネは絶対にしたくない。/チャンスと見たら、一気に攻め立てる。/『内容はどうでも、勝てばいい』/そういう考え方は俺の性にも考えにも合わないんだ」
いきなり引用から始めましたが、この言葉に「坂本博之」というプロボクサーのすべてが詰まっているような気がします。
坂本さんは、元日本ライト級チャンピオン、元東洋太平洋ライト級チャンピオンで、世界タイトルマッチを4度戦うも、ついに世界チャンピオンになることなく引退した名ボクサーです。生い立ちが過酷で、日々の食事に困り窃盗をしたこともあったようで、一時期は、児童養護施設で過ごしたこともありました。その半生は、テレビのドキュメンタリー番組でも何度か取り上げられていたので、ご存知の方も多いでしょう。
日本テレビが出版したこの本は、坂本さんの語りを読みやすくまとめている感じで、20分もあれば読めるほど親しみやすいものですが、印象的な部分がいくつかあります。そのうちの一つが、坂本さんのボクシング観。「平成のKOキング」とまで呼ばれた豪腕の坂本さんですが、倒すのはパンチ力ではなく、「気」だと言います。
「俺には昔から、『殺気と拳の力は比例する』という考えがあって、殺気を出すことによってパンチの力は増強するって信じてきた」
で、さらにこう続けます。
「じゃあ、精神力が強い者同士だったらどうなるか。/それは凄い試合になるよ」
凄い試合――ぼくたちはそれをはっきりと記憶しています。坂本さんにとっては負けた試合ですが、そのときの世界チャンピオンだった畑山隆則さんとのタイトルマッチは、タイトルマッチなんてことは二の次にした、男と男の意地のぶつかり合いでした。中盤以降、耳から血を噴き出しながら戦う坂本さんの姿は、忘れられません。そして、ほれぼれするような畑山さんのワンツーを喰らい、ゆっくりと崩れていく坂本さんのダウンシーンも......。
この試合は2000年10月11日に行われているのですが、同じ月に、畑山さんとは多少の因縁があった渡辺雄二さんというプロボクサーが引退しています。実は、渡辺さんは私にとって特別な存在です。というのも、私が初めてインタビューした相手が、渡辺さんなんです。
で、そのボクサー人生を書かせていただいた際、私は書き出しで、坂本さんと畑山さんの試合のことをちらりと触れました。それでハッキリと覚えているんですが、あの試合は、TBS系列で約25%(関東)もの視聴率を獲得していたんですね。
そういえばつい最近、25%をはるかに上回る視聴率を得た、注目の一戦がありました。でも、あれって、坂本さんの言葉を借りれば、「殺気」なんてあったのかなぁ。
坂本さん×畑山さん、畑山さんでいえば、史上最高の日本タイトルマッチと言われたコウジ有沢戦、日本ボクシング史最高の名試合と評判の高橋ナオトさん×マーク堀越さん――挙げればキリがないけど、勝つか負けるかじゃなく、倒すか倒されるかの試合こそを「意地のぶつかり合い」というわけで、少なくとも、途中の採点を聞いて、さばくラウンドを作っちゃうなんていうのは、大言吐く選手にあってはならないことと思うんだけど......。
あ、別にぼくは、彼ら――というか、世間的には特に亀田興毅さんに対してなんだろうけど、アンチというわけじゃないんです。ぼくは、すべてのプロボクサーを無条件に尊敬していますから。
ノンフィクションライターの故・佐瀬稔さんが、その著書『感情的ボクシング論』で、この現代の飽食の時代に、わざわざボクシングなどというストイックなスポーツに飛び込む若者を尊敬せずにいられないといった趣旨のことを書いています。ぼくもまったく同感です。
でも、そういう彼らだからこそ、判定による勝ち負けを競うのではなく、やるかやられるかという、命の削り合いを見せられるはずなんですよね。ぼくたちはその姿に感動するわけじゃないですか。
先述の渡辺さんはインタビューの際、「いつも相手を殺すつもりでリングに上がったし、それで死ぬことが相手にとっても本望だろうと思っていた」と言っていました。まさに殺気ですよね。ちなみに、渡辺さんは25勝23KO5敗1引き分けという戦績で、5敗もすべてKO負けだったはずです。文字通り、やるかやられるか、というボクシングスタイル。坂本さんが言う「殺気と拳の力は比例する」というのは、本当かもしれません。
そういう男気ある選手を思い出すにつれ、先日のタイトルマッチにはどうにも違和感を覚えます。勝ちゃあ、いいのか? せっかく騒がれて戦うなら、やっぱりそれらしいプロのスタイルがあるんじゃないの? なんて。
いや、繰り返しますが、アンチじゃないですよ。ただ、どっちが勝ってももっと熱くて爽やかな試合にできたはずなのに......って、とても残念に思っているだけなんです。
『壊れる日本人――ケータイ・ネット依存症への告別』 柳田邦男
09/11/27
モニターの心拍数ばっかり見て、死にゆく人の顔は見ない…
機械依存症の日本人、ディズニーランドにはケータイ持ってくるな!
東京ディズニーランドでは、見えないものがあるんです。尊敬する経済評論家の伊藤洋一さんがおっしゃっていました。そして、つい先日、実際に行って確認してきました。
確かにない。ありませんでした。電線が。
それはもう徹底していて、駐車場からも電線が見えませんでした。さすが、年間2500万人以上を集客する日本一のテーマパーク。「夢空間」を作るために、そのぐらい徹底して取り組んでいるのだそうです。
それなのに......。その日、園内のとあるアトラクションで40分待ちの行列に加わっていた際、私のすぐ後ろに並んでいた40代くらいの女性が、突然、携帯電話で話し始めたんです。それも、保険の営業の方のようで、かなり具体的な金額や条件なんかを大胆に口にするんです。正直、興ざめですよ。
そりゃ、待っている時間をどう使おうと自由ですよ。そもそも、他人の電話に耳をそばだたせるな、と"逆切れ"されるかもしれません。でもね......、そりゃあルール違反ですよ、やっぱり。私だって経営者の端くれで、いつ大事な電話がかかってくるか分からない毎日を送っているわけですが、それでも(というか、だからこそ)遊ぶときは遊ぶ、と決めて、携帯電話はあえて自宅に置いていくようにしているんです。それなのにすぐそばで仕事の話をされたら、私だって、自分の仕事を思い出しちゃうじゃないですか。でも、言っちゃ悪いけど、よほどのVIPでもなければ、半日くらい電話がつながらなくてもどうってことないでしょ?
なんて思っていたところ、書店で平積みされていた『壊れる日本人』(新潮文庫)を手に取りました。見出しに惹かれただけですが、柳田さんの著書だし、信頼して即購入。一気に読みました。
著作自体は月刊誌『新潮45』で2004年に連載されたものらしく、長崎県の小学校で起きた小学6年生の少女による同級生殺人など、当時、世間を騒がせた子どもの事件、生態、電子メディアをめぐる環境などがレポートされています。その中身はともかくとして、柳田さんの視点は「得るものがあれば、失うものがある」として、現代のケータイ依存、テレビ、ネット漬けを憂い、その一方で、日本語や方言の復権などを取りかかりに、言うなれば情操教育に目を向けていきます。
特に印象的だった指摘は人が死ぬ場面の描写で、柳田さんは、「死期に立ち会いながら、人はモニターを通して死を知る」という何とも象徴的なことを書きます。以下、本文から抜粋します。
「いよいよ死期が近づくと、病室に詰めている家族の眼は、どうしてもモニターに向けられてしまう。心拍数が減り、心拍の波形がだんだん平坦に近づいてくると、家族の眼はモニターに釘づけになる。患者の枕許で手を握り、顔を見つめて、別れの言葉をかけるという、古来誰もがやってきた大事な別れの行為を忘れているということに、誰も気付かない。そして、心拍がなくなり、波形が平になり、医師がご臨終ですと言うと、家族はようやく《ああ、死んだのだ》と思い、死者のほうに顔を向けることになる」
確かに私たちは、機械に依存し過ぎ、大事なものを見失っているのかもしれません。
そんななか、柳田さんが提唱するのは、ノーケータイデー、ノーテレビデーです。週に1日でも、携帯電話やテレビを使わない日を作ろうと訴えます。
一応付記しますが、柳田さんは、携帯電話やネットの便利さを認めています。そのうえで、便利さの代償で失うものがあるから、それを取り戻す日を作ろうよというわけです。私に言わせれば、テーマパークに携帯電話を持ち込むな! ということですね。
ちなみに同書には、「再生編」もあるようです。この正月には、テレビを消して、ぜひそれを読んでみようと思います。
※冒頭の伊藤洋一さんの発言については、記憶で述べています。文献等を確認しているわけではありません。万一、誤りでしたら、ご指摘ください。
『聖堂の日の丸 奄美カトリック迫害と天皇教』 宮下正昭
09/10/05
綿密かつ豊富な取材に基づく力作。
記録として素晴らしいが、読むのは疲れる
ぼく自身はちょっと仕事上の理由があってこの本(南方新社)を読んだのですが、読み物として面白いかと聞かれると、正直微妙な一冊です。
ただ、記録としては素晴らしいし、取材・執筆を職業とする端くれとして、大いに刺激を受けました。
この本をお薦めするとするなら、以下の人たちには、有意義ではないかと思います。
・キリスト教迫害に興味がある
・地域共同体(の負の面)に興味がある
・戦時下の日本軍の人心支配に興味がある
・ポピュリズムに興味がある
・奄美大島に興味がある
本書は大正から昭和初期にかけて奄美大島で起こったカトリック迫害の事実を追ったドキュメントで、証言者が実名(ときに写真入り)で登場する、その意味ではなかなか生々しい内容です。迫害のクライマックスとして、教会の炎上があるのですが、その当時、放火だと噂されます。この著者は、その実行犯と疑われた男性にも、直撃取材を試みるんですね。男性はすでに80代で、答えている内容に特異性はないのですが、迫害される側、迫害する側の両方に公正にあたっていく取材姿勢は好感持てます。
で、結論というか、本書のテーマとしては、「大衆」というものの恐ろしさがにじみ出ます。最近の政治を見ていても感じることですが、「衆愚政治」とはよく言ったものです。「空気」で感情が激化し、感情が過剰な行動を生み出してしまう――。
著者は奄美大島を日本全体の縮図と捉えているのですが、その視点は、割と重要なものに感じました。つまり、島国、ということです。地域共同体特有の暗黙のルールとか既存のしがらみとか人間関係とかがあって、そういうどろどろしたものが、理性だけでは抑えきれない大きなうねりを生むことがあるわけです。人間社会の面白さであり、怖さですね。
そう、一応付記しておきますが、奄美大島ではカトリック信者が大正時代の一時期、急速に増えたことがあるそうです。その背景には、島民が本土(特に薩摩=鹿児島)から隷属的扱いを受けていたこと、それまで、ユタなどの土着宗教以外にこれといった宗教がなかったこと、などが挙げられるようです。カトリックというか、キリスト教が根付きやすいベースがあったのですね。
面白いといっていいか分かりませんが、なぜカトリックだったかというと、プロテスタントより数日早く布教されたからだそうです。カトリック神父に続いて数日後に入島したプロテスタント牧師は、「住民のカトリック熱を見て、(中略)沖縄へ去った」そうです。そのぐらい、急速にカトリックが広まったわけですね。
見ようによってはその広まりもまた「大衆」であり、それを畏怖した「大衆」が迫害を行ったと言えるのかもしれません。