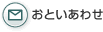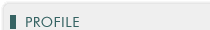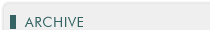志賀泉の「新明解国語辞典小説」
- あ
- 09/07/07
- い
- 09/07/30
- う
- 09/08/15
- え
- 09/08/31
- お
- 09/09/13
- か
- 09/09/24
- き
- 09/10/08
- く
- 09/10/28
- け
- 09/11/19
- こ
- 09/12/03
- さ
- 09/12/13
- し
- 09/12/27
- す
- 10/01/24
- せ
- 10/02/15
- そ
- 10/03/04
- た
- 10/03/24
- ち
- 10/04/12
- つ
- 10/05/03
- て
- 10/05/16
- と
- 10/06/04
- な
- ―
- に
- ―
- ぬ
- ―
- ね
- ―
- の
- ―
- は
- ―
- ひ
- ―
- ふ
- ―
- へ
- ―
- ほ
- ―
- ま
- ―
- み
- ―
- む
- ―
- め
- ―
- も
- ―
- や
- ―
- ―
- ―
- ゆ
- ―
- ―
- ―
- よ
- ―
- ら
- ―
- り
- ―
- る
- ―
- れ
- ―
- ろ
- ―
- わ
- ―
- ―
- ―
- ―
- ―
- ―
- ―
- ん
- ―
と
とら
10/06/04
とら【虎】
アジア特産の猛獣。背中から腹にかけて黄色の地に黒いしまが前後方向に対して直角に有る。口が大きく、鋭い牙(キバ)と爪(ツメ)を持ち、眼光が鋭い。皮は敷物などに用いられた。〔ネコ科〕
ぼくの学校にはトラがいます。
どうぶつ小屋をすみかにしているけど、かっているわけではありません。
いつからトラがすみついたのか、わかりません。お父さんが小学校に入った時にはもういたというから、ずいぶんむかしからいるようです。
お父さんが人から聞いた話だと、どうぶつ小屋にははじめ、うさぎとモルモットとインコがいました。ある日の朝、しいく係がエサをやりに小屋に入ったら、うさぎもモルモットもインコもいなくて、かわりにトラがねていたそうです。たぶん、トラがみんな食べちゃったのです。けれど不思議なのは、どうやってトラがどうぶつ小屋にしんにゅうしたのかで、なぜかというと、小屋にはカギがかかっていたからです。
しいく係はびっくりして、しょくいんしつに走っていって先生にトラがいることを教えましたが、先生は学校にトラなんているはずないと言ってしんじませんでした。じっさいにどうぶつ小屋に行ってトラがねているところを見ても、いるはずがないものはいないのだと言いはって、だからぼくの学校にトラはいないことになっていますが、じじつとしてトラはいます。いるものはいるのです。
ぼくがはじめてトラを見たのは入学式です。体育かんのえんだんの、校きを立ててある横にトラはねそべって、首だけ上げてぼくたちを見ていました。じっとしているので、はじめはかざりだと思いました。校長先生や、PTA会長も、トラをぜんぜん気にしていませんでした。そのうち、トラがうごいて前足をぺろぺろなめました。シタがすごく長かったです。ぼくはおおっと思いました。でも、先生や、ほかの子どもや、おとうさんやおかあさんが、みんな静かにしていたので、ぼくもだまっていました。本当はトラなんかいなくて、ぼくにだけ見えるまぼろしかなと、思いました。でも、入学式がおわったら、みんなが「あのトラすごかったね」とか「ネコみたいだったね」とか、ひそひそ話したので、やっぱりトラはいたんだと、ほっとしました。
子どもぶんこで、トラについてしらべようとしたら、どうぶつずかんの、トラのページだけ、やぶけてありませんでした。
トラは、夜はどうぶつ小屋でねますが、朝になると、学校のどこでも、じゆうに歩きます。朝礼の時とか、校長先生がお話しをしている台の下で、体をなめたりしてます。国きけいようとうを、ツメとぎの柱にしてます。ろうかを歩いてると、するどいツメがゆかを引っかく、カシャカシャという音がします。じゅぎょう中でも、きょうしつの後ろからのっそり入ってきて、つくえの間を歩きまわります。先生はなにも言いません。きょろきょろトラを見てると、よそ見をするなと、先生にしかられました。トラは、くんくん鼻をならして、ぼくたちの足のにおいをかいだり、つくえの中に鼻をつっこんだりします。つくえの中に、きゅうしょくののこりのパンをかくしていると、それを取って食べたりします。食べる時は、二本の前足でパンをおさえて、がつがつ食べます。食べ終わると、かならず、シタで鼻をなめてから、前足をなめて、それから、床に落ちたパンくずもきれいになめます。
じゅぎょうをしている先生の横で、ねそべることもあります。トラはおとなしいので、先生はなにも言いません。あおむけになって、しっぽをふると、ネコみたいでかわいいです。先生が黒板をふいて、チョークのこなが顔に落ちてきて、トラはクシュンとくしゃみしました。ぼくたちはクスクスわらいました。先生はしずかにしなさいと言いました。
ぼくたちはだんだん、トラのそんざいになれて、気にしなくなりました。でも、ろうかの手あらい場の下にいて、気がつかなくて、ぼくが手をあらってる時に、おなかをつっつくものがあるなと思って、下を見たら、トラと目があって、そんな時は、やっぱりぎょっとします。
前に、じゅぎょう中に、おしっこがしたくなって、先生に言ってトイレに行こうとしたら、トラがろうかをふさぐようにして寝そべっていて、こまりました。どうしようかまよったけど、おしっこがもれそうなので、こわいのをがまんして、トラの後ろのほうを、しっぽをふまないように気をつけながら、とおりました。そうしたら、トラがのそのそついてきました。走って、トイレのうんちのほうに入って、カギをしめました。トラが、ツメで、ドアをカリカリ引っかく音がして、こわくて、トイレに入っているのに、おもらしをしてしまいました。休み時間になって、きょうしつにもどったら、みんな笑いました。
ともすけ君が、ぼくのことを「しょうべんたれ」と言って、からかいました。
次の日、ともすけ君はいなくなりました。トラが食べたのだとみんなうわさしました。でも、学校にトラはいないことになっているので、ともすけ君は転校だそうです。
トラは、いじめっこを食べてくれます。でも、いじめられっこも食べます。いじめっこでもいじめられっこでもなくても、食べます。だから、だれでもいいみたいです。男の子でも女の子でも、太っててもやせてても、成せきゆう秀でも頭が悪くても、かんけいないみたいです。
トラが子どもを食べてるところを見た人はいません。肉の食べのこしや、服のきれはしや、血のあとものこりません。でも、子どもがいなくなると、トラの口のまわりの毛に血みたいなものがついてるので、食べたんだなとわかります。でも、学校にトラはいないことになっているので、トラをたいじしようと考える先生はいません。いないものはたいじできないからです。トラは、大人を食べないので、先生はへいきです。
トラに食べられた子どものせきには、よそから転校してきた子がすわります。それで、みんな、なんとなく、はじめからそんな子どもはいなかったんだなという気になります。
おとうさんも、小学生の時、友だちをなん人か、トラに食べられたそうです。でも、おとうさんが言うには、がっこうにトラがいることが、きょういくいいん会にばれると、校長先生がクビになるので、かくしているそうです。でも、運動会や学習はっぴょう会に、きょういくいいん会の人も来るので、その時に、トラを見ていると思います。ぼくがそう言うと、おとうさんは、トラがいることが文ぶか学しょうにばれると、きょういくいいん会の人がクビになるので、やっぱりかくしているのだと、言いました。
トラがいつまで学校にいるのか、わかりません。ぼくは学校を卒業したので、トラに食べられる心配はなくなりました。大学を卒業し、社会人になり、子どもの頃を思い返すたび、あのトラは何だったのだろうと、不思議になります。なんにせよ、トラのいる学校は僕にとって、遠い思い出になっていました。
しかし、結婚して子供が生まれ、その子が学齢期を迎えると、虎の棲む小学校はあらためて現実問題として我が身に迫ってまいりました。
先日、教育委員会の役人が我が家を訪問し、入学の手引きを置いて帰りました。虎について質問できる雰囲気ではありませんでした。出来れば、息子をあの学校に入れたくはありません。しかし義務教育は憲法によって定められていますし、息子を私立に入れるだけの経済的余裕は私にありません。息子を、私や私の父と同じ小学校に入れるしかなさそうです。それに、みんなが隠しているだけで、あるいは気づかないだけで、本当は、どの小学校にも虎が棲んでいるのかもしれないではありませんか。
児童が虎に食べられるといっても、数としてはごく少数です。虎がいるから学校に行くなと言うのは、交通事故に遭うから道路を歩くなと言うようなものかもしれません。
ただただ私としては、息子が虎に食われることなく無事に卒業してくれることを祈るばかりです。
と
とうしみとんぼ
10/06/04
とうしみとんぼ【灯心とんぼ】
〔「とうしみ」は「とうしん」の雅語形〕トンボの一種。からだは細くて緑色。羽が弱い。イトトンボ。とうすみとんぼ。
携帯電話が手から滑り落ちた。足下に落ちたそれを拾おうと、慌てて腰をかがめた拍子に、つま先で蹴ってしまった。
橋の上でのこと。集団下校の帰りだった。
携帯電話は菜々子の指先から逃げ、菜々子の前を歩く、集団下校の仲間の足下へと滑り込んだ。誰かの足が携帯電話を蹴り、別の誰かがさらに蹴った。携帯電話は彼らの足下から弾き出され、ガードレールの下をくぐって川に落ちていった。
またたく間の出来事だった。声を上げるひまもなかった。
偶然? 誰も気づかなかったの? うそ。わざとだ。菜々子は仲間の背中をにらんだ。みんな黙々と歩いているが、背中で揺れるランドセルがくすくす笑っていた。
携帯電話はコンクリートの川底に沈み、水色のボディが光の屈折でゆらゆらしていた。
菜々子の心が、ポキリと折れた。
やっぱり、山村留学に行こう。折れた心で、そう決めていた。
菜々子の小学校では、生徒は学校に携帯電話を持ち込んではいけない決まりだ。菜々子は特別に許可をもらい、携帯電話を肌身離さず持ち歩いていた。
菜々子は五年生だ。お母さんは首都高速道路で交通事故に遭い、それからずっと、意識をなくして入院している。いま、菜々子はお父さんとふたり暮らしだ。緊急の場合にはすぐさま連絡がとれるようにと、先生が配慮してくれたのだが、クラスメイトの中には特別扱いをやっかむ者もいた。
だから、めったに人前では携帯電話を使わない。さっきは自分の携帯電話と同じ着信音が聞こえて、もしやと思い手に取ったらば、自分のでない、たまたますれ違った大人の携帯電話だった。ほっとして、手がゆるんだ。とたん、するっ。かしゃん。
電話の音に敏感になっていた。お母さんの事故を最初にしらせた、家の電話の呼び出し音が耳に甦るからだ。トラウマになっているのかな、と思う。静まり返った教室でも、着信音を空耳に聞いた。そっと携帯電話を手にして、先生に注意された。クラスメイトの視線が痛かった。消え入りたいくらい、苦しかった。
お母さんの事故以来、心が不安定だ。お父さんは毎日仕事帰りに病院に寄って、菜々子の面倒を見きれない。「五年生になったら一年間、伊豆の山村に留学してみたらどうか」とお父さんが言い出したのは去年の十一月だった。
事故から半年が過ぎていた。回復の見込みはなく、かといって、容体が急変する怖れも遠退いていた。もしものことが仮に起きても、半日で病院に駆けつけられる距離だ。
イヤ。絶対イヤ。菜々子は拒否した。お母さんの近くにいたかった。田舎暮らしなんてしたくなかった。なにより、お父さんに厄介払いされるみたいで怖かった。頑固に拒みとおして、五年に進級した。
なのに、川に沈んだ携帯電話を橋の上から見下ろした、そのとたん、あっけなく心が折れた。ぽきん、という音まで聞こえた。
それが四月の終わりのことだ。早々に手続きをすませ、五月の連休明け、菜々子の山村留学は始まった。伊豆半島の付け根にある静かな山里だ。
菜々子は区長さんの家にホームステイした。農家で、広い庭と長い縁側があった。子供の日は過ぎたのに、鯉のぼりが庭に泳いでいた。緋鯉が真鯉の上にあった。菜々子の肩からどっと力が抜けた。力が抜けすぎて、理由のわからないまま、涙がぼろぼろ零れた。
「菜々子ちゃん、スイカお願い」とおばさんに言いつけられ、菜々子は「はあい」と返事し、サンダルをつっかけ裏庭に出た。井戸にスイカを冷やしてある。
屋根があって、滑車がついて、日本昔ばなしみたいな井戸だ。ここで野菜を洗ったり冷やしたりする。屋根には苔が生え、草が伸び、大きな穴が開いたままになっている。
蓋をのけると、暗い水のにおいがする。吸い込むと肺の中まで暗く染まりそうな、重いにおい。慣れない頃は井戸に落ちてしまいそうで怖かった。覗き込むと、すっと、頭が重くなる。井戸の底は地球の中心に近いぶん、重力も強いのではないか。
いまは平気だ。井戸に引き込まれそうな力はいまも感じる。ただ、重力にあらがうだけの踏ん張りが、菜々子の足腰についたのだ。
井桁(いげた)に手をかけ、覗き込む。空の光が、屋根の穴をとおり抜け、暗い水面に円く差し込む。円い光の中心に浮いた黒い玉が、スイカだ。スイカに菜々子の影が重なる。
頼りない影。自分の影が自分でないみたいな。井戸は深くて、お母さんの眠りも、これくらい深いのではないかと考える。事故後しばらくは、呼びかければ脳波計が反応した。見た目に変化はなくても、声はちゃんと届いていた。それがひと月もすると、声が届かなくなった。眠りが深くなったのだ。てのひらをペンでつつけばわずかに反応する。反応がなくなれば脳死だと、お医者さんは言った。
脳死? 脳死というのは、眠りの底が抜けるということ。
よく見れば、井戸の底の水面はかすかに揺れている。井戸水は流れている。おじさんがそう教えてくれた。井戸水が流れる? ああ、地下水が井戸をとおり抜けていくのさ。
スイカは、ロープを結わえた笊(ざる)に載せてあるので、ロープを手繰り寄せれば引き上げられる。井戸で冷やしたスイカは重くなる。これは菜々子の発見だった。
濡れたスイカを抱え、井戸端にしゃがむ。風が吹いて竹藪がざわめく。蝉の声は遠い。
いつの間にか、井桁に蜻蛉(とんぼ)がとまっていた。
「あ、イトトンボ」菜々子は呟いた。
井戸水のにおいに誘われたのだろう。蜻蛉だって、よく見ればそれなりに凶暴な面構えなのに、これにはそれがない。カゲロウのようにはかなくて、こわれやすく、消え入りそうで。なにを食べるのだろう。水だけ飲んで生きていそうだ。全身が神経の糸でできているような、ささやかな生き物だ。すっと飛び立てば、すぐ空中にまぎれて目で追えなくなる。目に見える世界と見えない世界の境を、イトトンボはすずやかに飛ぶ。
五年生は、菜々子をふくめて四人いた。六年生は二人いて、ひとつの教室で一人の先生が授業を同時進行させた。勉強がはかどらないだろうと思ったら、そうでもなかった。むしろ都会の学校より授業の中身が濃くて、びっくりした。
教科書の授業のほかに、五年生と六年生は自然研究という授業があった。留学の子と地元の子が二人ひと組になって、身の回りの自然からテーマを選び一年かけて研究する。
菜々子は条太郎という男子と組んだ。男子と組むだけでも嫌だったが、条太郎が研究していたのはクモだった。空の雲? ううん、虫の蜘蛛(くも)。げっ。
ヤだ、ぜったいヤだ。ヤダって言ったって俺もうやっちゃってるし、おまえと組むの決めたの先生だし。おまえなんて呼ばないでよ。
条太郎は一人で研究をしていたのだ。後から来た転校生が女子だからって、有無は言わせなかった。
「じゃあ、俺は蜘蛛を調べるから、おまえ網の担当な。それでいいだろ」
「網? 蜘蛛の巣?」
「巣じゃなくて網。ウェブ。蜘蛛の巣なんて言うのは素人だ」
「素人でいいけど」
「蜘蛛はかしこいんだよ。たとえばさ、なんで蜘蛛は自分の糸に足をくっつけないで歩けるか、おまえ知ってる?」
「おまえなんて呼ばないでよ」
「ネバネバがあるのは横糸だけで、縦糸にはないから。蜘蛛は縦糸だけ伝って歩くんだ」
毎週金曜日の午後は、自然研究の時間だ。条太郎と菜々子は蜘蛛を探して神社やお寺を歩いた。蜘蛛がいそうだとにらむと、条太郎は他人の家の庭でも平気で入った。
菜々子は条太郎に、蜘蛛の網を標本にとる方法を教わった。これと決めたら、白のラッカーを網に吹きかけて見やすくし、黒い台紙に水糊を塗って、ぺたんと貼りつける。一発勝負なので緊張した。失敗すると糸が切れたり、貼りつける瞬間に網がずれたりで、台無しになる。うまくいけば、標本は美しかった。蜘蛛の網はそれぞれ個性的で、機能的で、ある意味、知的だった。
条太郎は種類ごとに分けて虫かごに蜘蛛を飼っていた。蜘蛛を飼うなんて、どういう神経だろう。条太郎の虫かごを菜々子はなるべく見ないようにした。網をきれいだと思えるようになっても、蜘蛛そのものはやっぱり怖い。網の中心でじっとしているならまだいいけど、動き出すとぞっとする。背筋に寒気が走る。
いちど、条太郎が蜘蛛の糸を指先でつまみ、小さな蜘蛛をぶら下げたまま菜々子の鼻先に突きつけたときは、手にした図鑑で思いきり殴ってしまった。「冗談だよ冗談」と言いながら条太郎は鼻を押さえたが、てのひらの隙間から見る見る鼻血が流れ出した。
それからしばらくは、教室にいても、お互い口をきかなかった。
仲直りはちょっとしたきっかけだった。
庭に立っていたら、ひと筋の糸が微風に乗ってふうわりと目の前を流れていったのだ。目に見えない細さだが、光の当たり具合で部分的に白く光ったり消えたりした。
あっ、蜘蛛が糸を飛ばしてるんだ。
心が躍り、菜々子は条太郎の家に電話をかけた。条太郎は自転車を飛ばしてやってきた。家のひさしから庭のモチノキにかけて、糸はつながっていた。七、八メートルはある。糸を伝う蜘蛛を見て、条太郎は「オニグモだ」と断定した。茶色くて大きな蜘蛛だ。菜々子はスケッチブックを開き、網を作る手順に即して何枚も写生していった。
オニグモは急き立てられてでもいるみたいにそそくさ働いた。かなり大きな網で、人間にたとえれば、校庭いっぱいに網を広げるのに等しい。
「あんまり大きくし過ぎて、不安にならないのかな」
菜々子はオニグモの気持ちになった。蜘蛛に感情移入したのは初めてだ。
「いっぱい糸を使えば、それだけたくさん獲物を仕留められるから」条太郎は言った。
けれど、菜々子が感じた不安はそういうことではなかった。
オニグモは空そのものに網を張っているふうに見えた。空の途方もない広さに見合うだけの網を張ろうとして、網を大きくすればするほど、自分はちっぽけな存在になり、身の置きどころをなくしてしまうのではないか。空の一角で、光や風に体をさらして待つだけの身になり、寂しさに押し潰されそうにならないのだろうか。
自転車のスポークの形に似た、放射状の縦糸を張り終わり、オニグモはその中心から渦を描くように横糸を張りめぐらしていく。仕上がりつつある網の向こうで、空は赤みを帯びていった。山の端に積み重なって湧き立つ雲が、夕陽をはらんで燃え上がる。夕陽はスケッチブックを照らし、条太郎もオニグモも照らした。条太郎の顔を、きれいだと菜々子は思った。整った顔立ちだとは認めていたが、きれいだと思ったのは初めてだった。
「おまえ、蜘蛛を気持ち悪いと思ってるだろ」条太郎は言った。「蜘蛛は弱い生き物なんだ。弱くて臆病なんだ。網っていうのはさ、弱くて臆病なやつが生き延びてくために発明した、知恵の結晶なんだ」それから、「だから網は美しいんだ」と付け加えた。
美しい、なんて言葉を照れもせず条太郎が口にしたから、菜々子はびっくりした。
条太郎の目は澄んでいた。見るものと見られるものがひとつになっていた。蜘蛛の網の中心に条太郎はいた。そこがいまの条太郎の、世界の中心だった。
すっかり日が落ちてあたりが暗くなった頃、網は完成した。条太郎は菜々子がホームステイしている家で、夕飯を食べて帰っていった。
夜更けに目覚めた。蚊帳の中で。蚊帳は蜘蛛の網を思わせる。菜々子は、夜闇の庭に広がる網を思った。いまも網の中心で息をひそめているはずのオニグモを思った。
菜々子は夢想した。網の中心にいるオニグモはお母さんだ。お母さんが夜空に網を広げている。菜々子は網の中心から遠く離れ、端っこで暴れる羽虫だった。ワタシハココニイル。いくらばたついても、お母さんは気づかない。ワタシハココニイル。必死で羽を震わせても、震動の波は網に吸収され、深く眠ったお母さんを揺り動かせない。
そんな夢想をして、菜々子は泣いた。
菜々子が初潮を迎えたのは夏休みの四日前だった。
予感はあった。少し前から下腹が重苦しかった。生理のことは教わっていたので、それかな、と感じながら、認めるのが怖くて予感を遠ざけていた。来なければいいのに。ずうっと来なければいいのに。なのに、とうとう来た。午後の時間。よりによって体育の授業中に。太陽が暗くなった。黒い太陽が校庭から熱を奪っていった。汗が冷えて、菜々子はへたり込んだ。
保健室には生理用品も替えの下着もあった。こんなの、なんでもないことなんだよ、というように。ブラウスとスカートに着替え、ベッドに横になって校庭の声を聞いてると、世界中のなにもかもが自分から遠ざかっていくようで、せつなかった。
生理になんてなりたくなかった。子供のままでいたかった。妊娠できる体になったのかと思うと、体の中が暗くなった。自分の体がやましいものに感じられた。
お母さんを思った。これでお母さんと同じだ。自分の体の暗さが、お母さんの眠りの暗さにつながっているように思えた。
午後の時間をずっと、ベッドで過ごした。放課後になっても起き上がれなった。ベッドは白いカーテンで人の目から隠されている。カーテン越しに、膝をすりむいた下級生の泣き声を聞いた。すでに初潮を体験した上級生が訪ねてきて、短い話をして帰っていった。それ以外は放っておかれた。廊下を走る音がした。たてぶえが鳴っていた。いろんな音が遠く近く聞こえ、身の置きどころがなくなりそうで、つらかった。
風が吹いて、窓のカーテンがふくらんだ。
蜻蛉がすうっと飛んできて、窓の敷居に止まった。あっ、イトトンボ。
細い尻尾を、ぴんと伸ばして、アンテナみたいに。菜々子はそっと指を伸ばした。イトトンボは糸を引くような軌跡を残して、窓の外に飛び去っていった。
菜々子は上履きをはいて、窓から外に下り立った。
裏庭は柵のないまま裏山につながっている。痛みの残る下腹を片手で押さえながら小径を歩き、菜々子は裏山へ入っていった。誰にも会いたくない。家に帰りたくない。森の奥深く分け入って、自分を消してしまいたかった。
怖いくらい旺盛に茂った枝葉が重なり合って光をさえぎり、森はほの暗い。歩めば土の陰気さが足下からわきたつ。自然がやさしいなんて、うそだ。やさしい自然なんて人の作り物なのだ。本物の自然はさびしい。ひとりぽっち、自然に包まれていると、心が押し潰されそうになる。
途中から道をそれ、岩を伝い、渓流に下りた。流れに足をひたすと、水の冷たさが下腹に響いた。そういえば、携帯電話、東京の川に落としたきりだ。あの携帯電話、いまも沈んだままだろうか。川底で、誰かからの電波を受け取ったりしないだろうか。
ナナコ。ナナコ。ナナコ。ナナコ。ドコニイルノ?
流れに逆らい、上流を目指した。歩くにつれて渓流の表情が険しくなり、水のにおいが濃くなっていった。水音は鋭さをまし、菜々子の体を包み、削いでいく。このまま肉を削がれて細く細く細くとがり、イトトンボになりたかった。あんなふうに、はかない体になれば、体ぜんたい受け身になって、遠い電波をキャッチできるかもしれない。
渓流を登りつめると、いきなり視界がひらけた。目の前に滝があった。森の高みから溢れ出す水が、轟音を立てて落ちていく。飛沫(しぶき)が風に乗り、菜々子の顔を濡らす。菜々子はかたわらの岩に手をつき、細い息を長々と吐いた。
人の気配がして顔を上げた。なぜか、条太郎がいた。Tシャツが濡れて肌にぴったり張りついていた。滝が波紋を広げる滝壺の水辺で、腰まで水に浸かり、菜々子を見ていた。
安堵と恥ずかしさで、心臓がどきどきした。平然としている条太郎が憎らしかった。
「なにしてんのよ」菜々子は尋ねた。
「ミズグモ探してんだよ」条太郎はぶっきらぼうに言った。いつもと調子が違う。「ミズグモは水面すれすれに網を張って川虫を捕まえるんだ」
「条太郎君はきっと、前世で蜘蛛だったんだよ」
「おまえこそ、なにしてんだ?」
「おまえなんて呼ばないで」
「顔色悪いぞ。寝てなくていいのかよ。生理になったんだろ」
さっと、血の気が引いた。
「うっせえ、ばか」石をひろい投げつけた。小石なんかじゃない。
「うわ、当たる。マジあぶねえ。心配してやってんじゃねえかよ。うわっ。だから当たるって、なに怒ってんだよ。うわっ。止めろって」
「うっせえんだよ。この非常識。無神経。クモバカ。田舎者!」
一瞬の沈黙。条太郎はきょとんとして、それから、
「誰が田舎者だ!」突然、キレた。
肩をいからせた条太郎は急に男臭くなった。ケモノの形相を剥き出しに、波を蹴立てて突進してきた。
怖かった。仕返しされる、というだけでなくて、性的な意味で、襲われる、と思った。こんなふうに条太郎を感じたのは初めてだ。
菜々子は逃げた。滝壺の水辺を走り、足を滑らせて深みにはまった。水底につま先が届かなかった。泳げないわけではなかったが、叫ぼうとして思いきり水を飲み、パニックになった。波立つ水面の向こうに条太郎が見えた。飛び込んできた条太郎にしがみついた。あまり強く抱きしめたものだから、二人からまったまま、水底に沈んだ。水底の暗さが、目に残った。
気がつけば、頭からタオルをかぶり、膝を抱えて震えていた。
条太郎はすぐそばにいた。
夕焼けを映す滝壺の上を、たくさんの虫が飛び交っていた。
「さっき、家に電話した。もうすぐ迎えがくるから。俺のオヤジ、力持ちだから、おぶさって帰ればいい」
条太郎はやさしかった。
「ケータイ? 持ってたんだ」
「森に入るときは、まんがいちってことがあるから、オヤジのケータイを借りる」
「圏外じゃないんだ、ここ」
「県外? ここ、静岡県だよ」
「そのケンガイじゃない」
ばか、と呟いて、おかしくなった。くつくつ、腹を震わせて笑った。
「なんだよ、なに笑ってんだよ」条太郎はわかっていない。「変なやつ」
森の奥から夕闇は押し寄せ、翳りゆく滝壺に、滝ばかりが白く浮き立つ。
目の前の岩肌にイトトンボがとまっていた。ウエハースのように薄い羽が、茜色の空を映していた。じっとして、自分の弱さの中に、意識を細く研ぎ澄ましている。
緑色の細い尻尾をぴんと上向ける。その先が、ぽっと、青く灯った。アルコールランプの炎に似た、淡い光だった。
て
ていと
10/05/16
ていと【帝都】
皇居のある都会。〔明治以後は、東京を指した〕
屋上にのぼると、燕尾服の紳士がいた。
屋上の縁に立って、街を見下ろしている。
自殺志願者ではなさそうだった。ぼんやりたたずんでいる人の後ろ姿だった。
だいいち、飛び降り自殺に燕尾服はいくらなんでも似合わない。あれは晴れの舞台で着るものだろう。もっとも、考えようによっては自殺こそ晴れの舞台だと言えなくもない。
仮にそうだとしても、目の前の紳士は、背中がぜんたいにのほほんとして、追い詰められた感じがまるでない。ぜんぜん切羽詰まっていない。
だから、屋上に燕尾服がいたって別にかまわない。しかし、ひとつ腑に落ちない点は、彼がどうやって屋上にのぼったのかということだ。屋上の出入り口は施錠されていた。ドアの鍵を開けたのは僕だから間違いない。
社員のために開かれた屋上ではなかった。空調機械と電気設備が並び、無数の配管が縦横に延びるだけの屋上は、味も素っ気もない。もっとも、こういう殺風景な場所に癒される人間が世の中には少なからずいるもので、他でもない僕がそうなのだが、僕は窓ふき職人として仕事のためにここへ来たのであって、癒されるためではない。
原則、立入禁止の屋上だ。落下防止の柵も金網もない。膝くらいの高さの出っぱりがあるだけだが、紳士はそのぎりぎりに立って、妙にのほほんとした背中を僕に向けている。
会社のおえらいさんか。それなら屋上のドアくらい「開けゴマ」で開けてしまえる。礼服を着ているのだから式典があるのだ。いや、園遊会かも。早めに準備をすませて時間に余裕がもてた。空いた時間に思索にでもふけろうかと、人目を避けて屋上に出た。東京は本日も晴天なり、と、そんなところか。
いや、そんなことはどうでもよい。僕は迷っていた。どうしようか、困っていた。これから僕は、専門用語で笠木と呼ぶ出っぱりにロープをかけ、窓の外面へと下りていかねばならない。ブランコにすわり、オフィスで働くホワイトカラーをガラス越しに眺めながら窓をふくわけだ。そのためには燕尾服の紳士にどいてもらわないとならない。
なにを悩む必要がある。「どいてください」のひと言ですむ話ではないか。いやいや、そう簡単にはいかない。会社のおえらいさんは、たいがい神経質でわがままときている。ほんの気まぐれで出入りの業者の首を飛ばすくらい朝飯前のすっちょんちょんなのだ。
いや、僕は心配性ではない。経験でものを言っているのだ。三年前まで僕も会社員だった。それが、契約先の社長に「口のきき方が気に入らん」と嫌われ、それがうちの社長の知るところとなり左遷。いろいろあって首が飛び、家のローンが払えなくなり一家離散、浮浪者に転落という不条理な目にあってきた。
さいわい浮浪者生活は三ヵ月で終わり、現在の清掃会社にひろわれた。以来、組織というものにほとほと嫌気がさした。だから、ひとりになれる窓ふき職人を選んだのだが、この国に住んでいる以上、どこでなにをしようと組織は空気みたいについて回る。浮浪者の世界にだって上下関係の縛りはあったのだ。
風はない。絶好の窓ふき日和だ。しかし、空の高いところでびょうびょう風が鳴っている。油断はできない。大気は呼吸する生き物なのだ。
空は冷たく晴れ渡っていた。研ぎ澄ました刃みたいな青空で、朝だというのに星が見えた。夜空の星よりも冴えた光だ。
晴天の星空の下、紳士との距離が詰められないまま馬鹿みたいに突っ立っていた。
気配を察したのか、彼はおもむろに振り向いた。腰をひねるのではなしに、小さく足踏みしながら体を回していく。
後ろ姿の印象を裏切らず、紳士の顔はぬうぼうとしていた。
僕より少し年上。四十代の半ばくらい。丸メガネに小さくすぼんだ目。口髭におちょぼ口。整髪料でぺったりの髪。お茶目なふうで、冷たそうでもあり、気さくなようで、人ぎらいなふうでもあり、とらえどころがない。燕尾服がちっとも似合わず、胸ポケットから突き出たハンカチの端がこっけいなくらい。
紳士はゆらりと揺れた。片手を持ち上げ、肩の高さでひらひら振った。
それから、「やあ」と言った。
どこかで聞いた声。僕はなにかを思い出しそうになった。しかし喉まで出かかった記憶はすぐに、腹の底へ沈んでいった。僕の中のなにが反応したのかもわからなかった。
ただ、不穏な感じはしたのだ。表情は穏やかなくせに、声だけはなぜか暗いのだ。
「あ、どうも」僕は会釈した。「まいど、お世話になってます」
紳士は持ち上げた手で、鷹揚に僕を招いた。
「あの、イゴタ清掃です。窓ふきに来ました」
僕は用心しながら紳士のそばに近寄った。
「窓ふき? ああ、仕事ね。仕事をしたいの」紳士は言った。「高いね、ここは」
「いえ、慣れてますから」
「私は、高いところは苦手だな。馬に乗っただけで足が震えた。ははっ。馬の背というものはね、あれで乗ってみると存外に高い。しかし立場上、乗らないわけにいかなかった。馬上で威厳を保つのはね、君、簡単なようでいて、なかなか大変な仕事だ」
「はあ。乗馬をなさるんで」
「キリンはどうだろう。キリンのほうがよほど高い。君はキリンに乗ったことがあるか。ない。あ、そう。アフリカ人はキリンを手なずけようとは思わなかったのかな。ふむ、キリンの走る姿は見ていて優雅なものだ。しかし乗り心地はよさそうではない」
「あの、仕事してもいいですか」
どいて、と言う代わり、僕は紳士の横を指差した。
「仕事はね、もういいから」彼はこともなげに言った。
「は?」
「窓ふき、したいんでしょ。ここからロープを垂らして」
「あ、はい。それでですね」
「あれはね、いいから」
「いいから?」
「仕事もなにも、君は道具を携えていない。従って仕事にならない」
「へ?」言われて、気づいた。両手に仕事道具がない。足下を見ても、後ろを振り向いても、ないものはない。おかしい。どこに置き忘れたのだっけ。
「そういうわけだから、一服したらよろしい」
紳士はポケットから金色のシガレット・ケースを取り出した。並んだ煙草はフィルターの近くに菊の御紋が入っていた。話には聞いたことがある。恩賜(おんし)の煙草だ。
まじまじと紳士の顔を見た。あ、と息を呑んだ。あの人だ。二十年前に死んだはずの、あの人。いや、年老いて死んだあの人ではない。歴史の教科書に写真があったので覚えている。終戦直後、マッカーサーと並んで立っていた、若い頃のあの人だ。
「吸わないなら私がいただこう。君、すまないが火を」
煙草をくわえ、紳士は僕に顔を突き出した。すぼめたくちびるがまるで無防備だ。僕はポケットをまさぐった。ポケットからネジが出てきた。いったいなんのネジだ。思い出せなかった。
百円ライターは調子が悪かった。火花ばかり勢いよく散って、ついたと思ったら炎は横に倒れ消えてしまう。変だ、風もないのに消える。消える。消える。あ、ついた。
僕は炎を風から守るようにてのひらで囲った。紳士はてのひらの囲いに顔をうずめた。
顔を上げると、紳士は九十前後の老人になっていた。けむりを吐き出す。口と鼻ばかりでなしに、目から耳から頬から額から、顔じゅうから、ふわっと。吸ったけむりが肌を通り抜けているのだ。
「私は死んで久しいから自分では火をあつかえない。しかし君はまだ大丈夫だ」
「あの、気のせいなのかな。いっきに老け込んだみたいな」
しかし本当に驚きなのは、僕があまり驚いていないことだ。
「煙草を吸わないのならキャンディはどうか」
老人はポケットから棒つきキャンディを取り出し、僕に手渡した。チュッパチャプス。こんな味だっけか。眉間が割れそうに甘い。脳髄にずんと響く。
「甘いですね、これ。すごく」
「いまのうちだ。じきに味を感じなくなる。私はもうなにも感じない」
老人はもういっぽんキャンディを取り出し口にふくんだ。それからは、老人は煙草とキャンディを交互に口に運んだ。煙草のけむりはあいかわらず老人の顔ぜんたいから漏れ出ていた。
「味わうということも一種の習慣ではある。生命現象はぜんたい習慣で成り立っているから、習慣が消えればものの味もなくなるのだよ。逆に言えば、死んだ後も習慣が残っている間はものを味わえる。いまのうちしっかり味わうがよい」
「どういう意味ですか?」いやな予感がふくらんだ。
「ヨモツヘグイという言葉は御存知かな」
「いえ」
「そのキャンディがヨモツヘグイなのだよ。ヨモツヘグイをした以上、君もこちら側の人間になったわけだ」
気味が悪くなり、僕はキャンディを捨てた。
「まだわからないか。それは仕方がない。わかりそうにないから私がここに来たのであって、自力で理解できるなら私がここに来る必要はもとからなかった」
「なんだよ。誰なんだよ、あんたは」
老人の顔は四十代の顔に戻っていた。四十代の頬をキャンディがぷくんとふくらませていた。棒の末端をつまむとくちびるがすぼまり、ぽんと音がしてキャンディが抜け出た。くちびるの端が横に広がり、紳士はにっと笑みを浮かべた。
「まだわからない。わからないから私が告げねばならない。死んでいるのだよ、君は」
「うそ?」
「風が強い。こんな日の窓ふきは危ういことこの上ない。しかし君は風に気づかない。なにゆえか」
紳士はキャンディで向かいのビルを示した。向かいの屋上には小さな神社があり、日の丸がはためいていた。なのに、僕は風を感じない。感じられない。紳士の髪にも乱れはない。毛のいっぽんも揺れてはいない。いったい、風はあるのかないのか。
「風が君の体をすりぬけているのだよ」
老人はキャンディの包み紙を指から放した。それは羽が生えたように飛んでいった。
僕は自分のてのひらを見た。てのひらは粉を吹いていた。手を叩くと粉は舞い上がった。ためしに何歩か歩いてみる。足の裏はしっかりとコンクリートの床を踏みしめた。躍起になって足を踏み鳴らす。なんだか頼りない音がした。
紳士はムーンウオークをしていた。
「こんなに元気な幽霊っているかよ」
腹が立ち、かたわらの配管を蹴った。がこんと鈍い音がして、足の甲がしびれた。刃物で刺せばきっと血が出る。ナイフがあれば俺は生きてると証明できるのに。
「いやいや、幽霊の側から見れば生きている人間こそ元気がない」
「幽霊に唾が吐けるか」ぺっと唾を吐いた。「小便だって出せる。出してみようか」
「お好きなように。出したいのなら出るかもしれない。しかし、だからといって君が死んでいる事実に変わりはない。さっきも話したとおり生きているとは習慣のことである。茶碗の持ち方から、細胞ひとつひとつの化学変化にいたるまで生命活動はこれすべて習慣によって維持されておる。いま君が自分を生きていると感じるのも単に習慣がそうさせているだけであって、内実はちっともと伴っていない」
「なにごちゃごちゃ言ってんだよ。いつ俺が死んだんだよ。ちゃんと朝起きて、飯食って家を出て、ちゃんと電車に乗った。それから―」
それから? それからどうしたっけ? それから先の記憶がない。いきなり屋上の記憶に飛んでいる。
「わからないかな。君はさっき、そこのドアを開けもしないですり抜けていったのだよ」
不意の無力感が、僕を襲った。
紳士があらためて差し出した恩賜の煙草に手を伸ばした。諦めの境地で煙草に火をつけた。けむりを吐いたが、悲しみは湧いてこなかった。失業したときや浮浪者に転落したときのほうがよほど悲しかった。悲しみに身悶えして泣き狂ったものだ。
死んで悲しいというのは、僕が死んで悲しむ人がいるから悲しいのであって、悲しむ人がいなければ悲しむ理由もないのだった。いまはただ、ひたすらさびしいだけだ。
向かいのビルの日の丸が風にはためいている。旗の端のほうから布地が少しずつちぎれて風に乗り、飛んでいくように見えたのは、鳥だった。次から次へと日の丸から分かれて飛び立ち、めいめい、輪を描いたり宙返りをしたりしながら、晴天の星空をまちまちな方向へ飛び去っていく。
なにがさびしいのか。失うものがなにもないさびしさだ。この世になにも残せなかったさびしさだ。
「さびしがらなくてよい。たいていの人はたいしたものは残せない」紳士は人の心を見透かすようなことを言った。「残したと胸を張る人に限って、ろくでもないものしか残してないものだ」
「あのさ、人違いだったら悪いけど、あんたむかし、皇居に住んでたことなかったっけ」
「皇居を指して『空虚』と呼んだフランス人がいるが、大変な誤謬(ごびゅう)と言わざるを得ない。皇居ほど豊饒(ほうじょう)な場所が他にあろうか。ない。ないのだ。空虚ほど満ち足りているという東洋思想の逆説を西洋人は理解しない」
「俺、子供んときあんた見たぜ。植樹祭っていうの? すげえ車に乗って目の前を走っていくのを、俺ら沿道に並んで一生けんめい旗ふってたっけ」
「それは、どうも」
「でさ、なんであんた、こんなところにいんの? あんたら、死ねば特別な場所に行くと思ってたけど」
陛下、と呼ぶべきなんだろうと思いながら、「あんた」と呼んだ。
「特別ではないが、みなと同じでもない。むしろいまは、みなよりつらい」
「俺はあんたのこと責めないから。戦争だって、軍人の連中が勝手にはじめちゃったんだろ。学校でそう教わったけど。あんた、神輿に担がれただけなんだよな」
「君は前世から同じ考えだった。当時としてはまことに炯(けい)眼(がん)である。しかし、帝国憲法に定められた統帥権は、そんなに軽々しいものではない」
「俺の前世、見えんの? あんた江原ケイスケかよ」
「戦死した魂は成仏がむずかしいのだ。なにしろ、自分が死んだことにもなかなか気づかないくらいだ。長くこの世をさまよい、生まれ変わっても似たようなことを繰り返す。ほら、現に君がそうだったではないか。運命、と言っていいのかどうか私にはわからない。ただ事実として、そういう場合が多い。彼ら迷える民草に引導を渡すのが私のいまの務めだ。幾万の民草が私の名を呼んで死んだのだ。せめてそれくらいはせねばなるまい」
「引導って、この煙草? さっき、なんとかヘグイとか言った、あれのことか」
「君は、前世のことは忘れただろう。帝都防衛隊として、来たるべき本土決戦にそなえ特殊訓練を受けていたのだよ。いわゆるゲリラ部隊だ。君はビルの壁面をよじ上る訓練の最中に足をすべらせ、ロープが首にからまり宙吊りになって息絶えた」
「あほな死に方だな。聞いてあきれる。笑っちまうくらいだ。それも戦死のうちか」
「そう自虐的にならずともよろしい」
「自虐もなにも、そいつが俺だっていう自覚がぜんぜんないんだけど」
「いや、記憶を失っても痕跡は残るのだよ」
「ああ、デジャブってやつ。俺、あったよ。子供の頃なんか、しょっちゅうだった。不思議だよな、あれって」
「いや、デジャブではない。それは単なる思い込みでしかない」
「あっそ。別にいいけど」
恩賜の煙草は、いくら吸っても短くならなかった。煙草を持つ指の皮膚からけむりが漏れ出ているのに気づき、怖くなって煙草を捨てた。足で踏みにじろうとしても踏みにじれない。煙草を踏んだ足の甲を通り越して、けむりは立ち上っていた。
「時間というものを川の流れによくたとえるが、あれは間違いだ。時間は流れるのではなく降り積もると考えたほうが正しい。降り積もった時間はやがて地層を成す。おわかりかな? 新しい地層をめくればその下から古い地層が現れる。その地層をめくればもっと古い地層が現れる。幾層にも重なった地層の上にいまこの現在がある。さ、ここへ。遠慮せずに、私の隣へ。ごらんのとおり。時間の層をめくれば、現在の下に焦土と化した東京が現れる。さあ、思い出せるかな。君は前世でこの風景を見ていたはずだが」
「すげえな」
東京がいちめん焼け野原だ。ところどころ、瓦礫やトタンの隙間から、煮炊きのけむりが細く上がっている。けむりはまっすぐに立ち上り、空に吸われて消えていく高さを、さっき日の丸からちぎれて飛んでいった鳥が舞っていた。
「『東京物語』という映画があるのを御存知かな。御存知でない。まあよい。私はあの映画を何度も見た。よい映画だった。地方から出てきた老夫婦が高みから東京を見下ろす場面があるが、カメラは老夫婦の背中ばかり写して二人が見下ろしている東京の街をいっこうに映さない。二人が実際、なにを見ていたのかわからない。それがあの映画の勘どころだと思うが、どうか」
「あのさ、俺みたいなやつがこの世に腐るほどいるんだろ? そうだよな? そのひとりひとりと、こんなふうに付き合ってんの? あんた死んだよって教えて回ってんの。体がいくつあっても足りねえだろ」
「我が身がひとつとは限らない」
紳士は、向かいのビルを指差した。いつの間にか、元のままの東京だ。
向かいのビルは屋上に小さな神社がある。ほこらの扉がひとりでに開き、黒い革靴の足が突き出たかと思うと、タコが蛸壺から出てくる具合にぬるっと全身が現れた。軟体動物のようなぐにゃぐにゃの体がしゃんとすると、こちら側の紳士とうりふたつだ。そいつは赤い鳥居をくぐり、「やあ」と言うようにこちらへ片手を上げた。
こちらの紳士も、「やあ」と片手を上げた。それが合図だったように、向こう側の紳士の体がばらばらになり、無数の黒い鳥となって空へ散っていった。
「追って沙汰があろう。それまで、これでも舐めて待つがよろしい」
紳士はあらためて僕にキャンディを手渡した。キャンディはさっきほどは甘くなかった。甘いことは甘いが、脳髄にずんと響くような甘さではなかった。
紳士は、また老人の顔になっていた。
口髭が片方、斜めにずれている。あれ、つけ髭? と思っている間に、丸メガネのレンズが青白く光りだし、細胞がスパークしたみたいに体のあちこちが放電し、点滅を始めたかと思うと、ぷつんと消えた。ちりちりと電気のはぜる音が残った。
僕は屋上にひとり取り残され、あほうのようにキャンディを舐めながら、地上を見下ろした。眼下に広がっていたのは焼け野原の東京だった。ビルやら車やらでごちゃごちゃした東京よりも、むしろさっぱりとして気味がいいくらいだ。
これから沙汰があるらしいが、僕はどうなるのだろう。また生まれ直すなんて、考えるだけで疲れる。逃げちまおうかと、思いきって屋上の縁を蹴り、空に躍り出た。
落ちると思ったが、僕は空を飛んでいた。上空から見下ろすと、いちめん灰色の焦土の中にあって、皇居の森は島みたいだった。
くわえていたキャンディをうっかり落とした。皇居前の広場で泣き伏している兵士の頭に、それは命中した。
「あいたっ!」と声がした。
て
てのひら
10/05/16
てのひら【掌】
〔「手の平」の意〕手首から先の、物を握る時の内面の面。たなごころ。
君。
そう、これを読んでいる君だ。
俺は、君が誰だかわからない。わかっているのは、君が二十歳くらいの女性だってことくらい。名前も知らない。どんな声でしゃべるのか、知らない。好きな色は? 好きな食い物は? 好きな音楽は?
この文章は特定の個人、つまり君への手紙だ。けれど、君以外の人は読んでも仕方がないとか、無意味だとかいうのではない。君以外の人にとってのこれは、一個の物語だ。読んでほしい。読んでくれ。そしてなにかを感じ取ってくれたら、俺はうれしい。
この文章が君に届くかわからない。届かない確率のほうが圧倒的に高い。でも書く。書きたいから書く。なにかの奇跡でこいつが君に届くことがあるかもしれない。そしたら会ってくれ。話がしたい。方法はあとで記す。もちろんこれは罠なんかじゃない。君をはめるつもりはない。純粋に、会いたいだけだ。
君と俺は深夜のコンビニで出会った。覚えているはずだ。川崎と横浜を結ぶ産業道路から、北に折れて鶴見駅に向かう道の、十字路の角にあるコンビニエンスストア。ほら、対角線にエッソのガソリンスタンドがある、あの店。十字路に横断歩道はなく歩道橋だけがあって、その歩道橋の階段はぐるっと螺旋形になっていて、でも歩道橋を無視して道を横切る人は多いから、車にはねられて天国に直行した人の慰霊の花束が橋脚の真下にある。雨が降るとホームレスがやってきて花束に添い寝する。その歩道橋の目と鼻の先にあるコンビニ。俺はそこで働いている。週四回、夜の十時から翌朝の七時まで。
全国のコンビニの総数は四万店を突破した。去年一年間のコンビニ強盗の件数はおよそ九百件。四十四分の一の割合で被害に遭っている計算だ。数字だけ見るとまだまだこんなもんかと思えるけど、事件は都市部に集中してるし、商店街から離れた殺風景な場所にある店となると、事件の起きる確率はぐんと高くなる。つまりだ、俺が働いている店は、じゅうぶんヤバイわけだ。
働きはじめてすぐ、強盗対策の講習を受けた。ほら、蛍光塗料を塗ったカラーボールを犯人の背中にぶつけるってやつ。でも、そんなの実際には屁の役にも立たない。強盗がきたらさっさとお金を渡すべし。下手な抵抗は身を滅ぼす。これが現場の共通意見だ。俺もそう思う。
「去年の夏だっけ、暴走族くさいのが集団でやって来てさ、あからさまに行動がおかしいわけ。見え見えで万引きしてんの。あれ、俺なめられてんのって、むかついてさ、『おいこら』って注意したら、襟首つかまれてボコボコにされて、外に引きずり出された。まじやばかったよ。あいつら、車のトランク開けてたもん。もう少しで拉致されて山に埋められるとこだった」
これは相棒のアルバイトから聞いた実話だ。彼の体験から導き出される教訓は、「やばそうな奴には近づくな」だ。
どうしてこんな話をしてるかって? つまりだ、俺も日頃から犯罪に対する心構えは持っていたってことだ。犯人の目的がはっきりしていれば対処方はある。しかし君は? わからない。君の目的はなんだったんだ?
あの夜の相棒はお世辞にも仕事熱心と言えず、先輩格であるのをいいことに少年ジャンプやマガジンが届けば真っ先にひっつかんでレジの奥に引っこみ読了するまで腰が上がらないという最低の奴だった。
午前二時過ぎのことだ。相棒はレジの奥、防犯カメラの真下の、つまり死角になる定位置で手足を縮めて返品予定の雑誌を読みふけっていた。店内に客はいなかった。俺は店の奥で商品棚の整理をしていた。自動ドアが開いた。チャイムが鳴った。そして若い女、つまり君が入ってきた。
俺は防犯ミラーで君を見ていた。長い黒髪。臙脂色のブラウスに黒のオーバーコート。ジーパンにパンプス。別に変わったところはなかった。近所の人がコートを引っ掛けて買い物にきた、という感じだ。君は雑誌棚の前でいちど立ち止まり、腕を組みざっと棚を見ただけでドリンクのコーナーに移動し、そのまま俺の後ろを通り過ぎてお菓子のコーナーの前で足を止めた。チョコレートを選んでいるふうだった。店内のBGMはコンクリート・バッファローズの「千年の森」だった。覚えてる。俺はこの曲が好きで、こいつが流れるとつい鼻歌が出てしまうんだ。
ふと気づくと、君はレジカウンターの前にいた。相棒はいない。君は店員を呼ばず、店員を探してきょろきょろもせず、静かに立っていた。ほっといたら朝まで立っていそうな後ろ姿だった。あの野郎またさぼってやがる。俺は思わず舌打ちした。その音が聞こえたのか、君はゆっくりとふり返り、俺と目を合わせると軽く頭を下げた。「おいそがしいところまことにすいませんがレジをお願いします」とでも言いそうな上品な雰囲気だったから、俺は恐縮して小走りでカウンターに戻った。
カウンターには板チョコが一枚。深夜の買い物に板チョコが一枚、というのはあまりない。でも訝しがるほどのことではないので、俺はスキャナーでバーコードを読み「百六十円になります」と言った。君はポーチから財布を取り出した。小銭を出すのに少々手間取っている様子だった。俺は右手を宙に浮かして待った。すると君は、左手を俺の手に裏から重ねるように添え、右手で五百円玉を渡そうとした。
そのとき不審に思わなかったのか? 警察に何度も聞かれた質問だ。
「いえ、別に」俺は答えた。
「客がお金を払うにしては、不自然な仕草と思わなかったか?」
「店員がお釣りを渡すときにはよくやります。小銭を落とさないように」
「しかし、客のほうがそうすることはないだろう」
「あまりないですね」
「あまりない? まったくない?」
「まったく」
「それでも不自然とは感じなかったわけだ」
あんまり根ほり葉ほり尋ねるからうんざりした。まるで犯人の取り調べみたいだった。
お客さんの仕草を自然とみるか不自然とみるかは、動作や態度より、その人が醸し出す雰囲気に左右される。俺は君の仕草を自然に受け入れた。そう、ここまでは。
君は俺の右手に五百円玉を置いた。垂直に。そして手前にすっと引いた。てのひらの皮膚がぱっくり割れた。痛みは感じなかった。「あれ?」とだけ思った。「あれれ?」
見る間に血があふれ出てきた。痛みはあとから追いかけてきた。引っ込めようとした俺の手首を君は握った。激痛がてのひらから腕の表面を走り頭頂に達した。「いてえ!」俺は叫んだ。髪の毛が総立ちになった。なにが起きたのか、まったく見当がつかなかった。
真っ赤になった俺のてのひらを君は右手で握った。ふたりのてのひらの間から鮮血はぽたぽた滴った。振りほどこうにも腕がしびれて力がはいらない。それでも、必死でぐんと腕を引くと、君はがくんとカウンターの上に前のめりになった。
君。
君はあのときなにを考えていた?
俺は君の目を直視していた。君も俺の目を直視していた。
もし、君が凶暴な目で俺をにらんでいたら、もしくは錯乱した目を泳がせていたら、俺は恐怖のあまり自由な左手で君を殴っていたかもしれない。あるいは鋏で君の手を突いたかもしれない。けれど、どう言えばいいんだろう。君の目に怒りや怯えはなかった。俺になにかを訴えたがっているように見えた。この非常事態になに悠長なこと言ってんだって、人は思うだろう。でも、たしかに言えるのは、君の目は精神異常者や薬物中毒者のような平板な目ではなかったこと。ずっと奥の深い目をしていたことなんだ。
だから俺は、頭のどこかでは冷静でいられた。全面的には君を拒絶できなかった。これはなにか理由のあることなんだと考えていた。
ねえ君、これだけは教えてくれ。君は俺を狙っていたのか? たまたま俺がレジに立ったから俺を傷つけただけで、相棒がレジに立ったらやっぱり同じことをしていたのか?
考えすぎだろうか。俺はただの自意識過剰なんだろうか。
俺の声を聞いて相棒が裏の倉庫から飛んできた。同時に君は手を放した。俺がよろけて相棒にぶつかった隙に、君は板チョコをつかんで逃げていった。レジが開いていたので、相棒は強盗と勘違いした。
「どろぼう!」と見当外れのことを叫んだ。「どろぼう、どろぼう!」
相棒はカラーボールを手に君を追いかけ表に飛び出した。投げたボールは別人の顔面に当たり、事態はややこしくなった。でもそれは君にとってラッキーだった。そいつが相棒に食ってかかっている間に君はどこかへ逃げていったのだから。
五百円玉がカウンターに残されていた。俺のてのひらを切り裂いた凶器。君は、どういうつもりであんな細工をしたんだ? カッターの刃を、硬貨の端からほんの少しはみ出る具合に、セロテープで貼って。
それともうひとつ、君に言いたいことがある。俺はまだ、お釣りの三百四十円を君に返してない。
君が逃げた後、俺は血まみれのカウンターの上で、右手をおさえて痛みをこらえながら思い出したんだ。「あ、お釣り渡してねえ」って。
俺自身のことを書く。
二十六歳。出身は新潟県。横浜市鶴見区在住。ミュージシャン。履歴書の職業欄に「ロックンローラー」と書いて笑われたことがある。ロックンローラーとは生き方であって職業ではなかったんだ。
バンドを組んで横浜にある「ロドリゲス」っていう店を拠点にライブ活動をしていた。「していた」って過去形なのは、過去の話だからだ。ドラムを担当していた。わかると思うけど、俺の手は俺の商売道具だった。
包帯を巻いてる間、ドラムを叩けなかった。でも、さいわい傷は浅かったから、傷がふさがればちゃんと復活できたはずだ。
けれど、ライブハウスのスケジュールはびっちり決まってたからバンドの連中は焦った。どっかからドラマーを探してきて急遽メンバーに加えた。俺が復帰するまでの代役という話だったが、怪しいものだ。そいつ、埋もれた逸材だった。初めてそいつのドラムを聴いたとき、顔から血の気が引いたね。冷や汗が背中にどっと流れた。そんで悟った。「あ、俺もう終わりだ」って。
俺は元々ベース奏者だったんだ。それがあの連中とバンドを組んだとき、ドラマーがいなかったので俺がやることになった。正直、不本意だった。でも俺は文句もたれずドラムに打ち込んだよ。必死で練習した。そこそこは上手くなった。けど、魂じゃ乗り越えられない壁ってどうしてもある。もしかして俺、バンドの足引っ張ってんのかもってひそかに不安だった。でも、俺だって好きでドラマーに転向したわけじゃないから、そこんところはみんな理解してくれてた。なんだかんだいって、うまくやってこれたんだよ。
そう、あの事件までは。
日に日に空気が悪くなっていった。みんな、俺への態度がよそよそしくなった。そりゃあ、辞めてくれって口に出す奴はいなかった。けど俺も馬鹿じゃないからね。誰も俺の傷が治るのを望まなかった。それは肌で感じた。飲み会でも、畳の上に右手を置けなかったくらいだ。うっかり置こうものなら、誰かがうっかりのふりで俺の手を踏んづけるか物を落としそうで危険だった。
まさかと思うだろ。でも音楽やる人間ってそういうものだ。チャンスとみたら平気で人を裏切る。のし上がるためなら残酷になる。そうでなくちゃ駄目なんだ。だから、奴らの態度はある意味正解。奴らだけじゃなしに、ファンも、ライブのオーナーも、俺の復帰を望まなかったんだから。
傷が癒えても、しばらく包帯を外せなかった。結局、「後遺症が残りそうなんで」って嘘ついて自分から抜けたよ。「ああ、そりゃ残念だ」って、うれしそうにしてる仲間が悪魔に見えた。
あ、いや、君のせいだって責めてるわけじゃない。こうなったほうがバンドのためでもあり俺のためでもあったんだ。ひとりになったって俺はロックンローラーだ。俺はいまストリートに出ている。アコースティックギターを弾いて自作の歌を歌ってる。敗北でも転落でもない。いわば後ろ向きで前進。俺は自分の原点に戻ったんだ。
その他にも、言っておきたいことがある。
警察はまずコンビニ強盗の線を考えた。君が俺の手を握って放さなかったのは、俺の頸動脈も切って致命傷を負わせ、レジの現金を奪う計画だったんじゃないかという推理だ。でも、強盗にしちゃ変だ。だいいち、若い女性がひとりで強盗なんてあんまり聞かない。しかも素顔まるだしで。逃走を考えたらパンプスは履かないだろう、ふつうは。
それに、もし本当に君が俺の手首も切るつもりだったら、さっさと切ったはずだ。でも君はしなかった。レジの現金には目もくれなかった。
二番目に警察は、怨恨の線を考えた。犯人に見覚えはないか、女性に恨まれる覚えはないか、しつこく聞かれた。ない、と俺は言い切れなかった。店そのものへの復讐という線も考えられた。過去につかまえた万引き犯、売り上げをちょろまかすなどの罪でクビになった元アルバイトの記録を徹底的に調べた。
俺は、防犯カメラに残された君の画像と、過去数年間でしょっぴいた万引き犯や問題行動のアルバイトの画像を見比べた。なにせ膨大な数だったから半日がかりだった。万引き犯の画像をまとめて見ていくと、興味深い共通点があることに俺は気づいたが、それは横に置く。いま問題なのは、過去の万引き犯やクビになったアルバイトに君らしき人物は見当たらなかったことだ。
すると警察は個人的怨恨の線に戻り、俺の女性関係を探った。高校時代までさかのぼって、痛くない腹をさんざん探られた。なにせ俺はミュージシャンだから、警察官だって先入観で俺を見る。まったく、俺が取り調べを受けてるみたいでうんざりした。
第三の可能性は、愉快犯、通り魔的犯行。つまり「誰でもよかった」という最低のあれ。でもねえ、女性の通り魔っていうのはあまり前例がないんだよねえと警察は呟いた。だから俺もこの点は考慮しない。
俺に対する個人的怨恨だと、最も疑っていたのは俺の彼女だ。
俺は彼女と同居している。いや、これも正確には「していた」だ。
彼女はおっかけの女の子だった。ライブの打ち上げについてきて、そのあと俺のアパートまでついてきて、あれをしたあと自分の家庭的な不幸を切々と訴えるから「じゃあここで暮らせば?」と軽い気持ちで言ったら翌日の夜、本当に家出してきた。両手いっぱいに荷物さげて。びっくりしたね。それが二年くらい前の出来事だ。
わりとうまくやってたと思う。ただ、彼女には異常に嫉妬深いところがあって、それは彼女の家庭に問題の根本があるのだけれどそれは横に置いとくとして、なにせ自分が「お持ち帰り」された口だから俺の女性関係について疑うのは至極もっともで、いちど疑心暗鬼にかられると理屈も根拠もなく嫉妬がふくらんで爆発するまで止まらない。
そういうわけだからコンビニの事件も、俺に捨てられた女が復讐したのだと信じて疑わなかった。まあたしかに、俺もミュージシャンである以上、潔癖ではいられない。彼女と同居する以前は、何人もの女と別れたし、泣かせてもきた。でも、復讐されるほど酷い仕打ちをした覚えはない。「忘れてるだけよ」って彼女は言うが、元からない記憶は思い出せない。それでも彼女に言わせれば、思い出せないのは俺がそれだけ酷薄だからだ。
ああ、こうして書いてるだけで嫌になってくる。
利き手にぐるぐる包帯を巻いて、箸を持つのも歯磨きするのも難儀している俺にむかって「自業自得」と悪態をつき、ひとかけらの心配りもなかった。
「傷を見せて」としつこくせがむから包帯をほどいて見せてやったら、傷の縫い目がなまなましい俺のてのひらに露骨に眉をしかめて、ひと言、「キモイ」。
キモイだよ。ぶち切れたね、俺は。すさまじい喧嘩になって、それで終わりだ。彼女は荷物をまとめてアパートを出ていった。
怨恨もなにも、君と俺は初対面だった。「初対面」って言い方は変だけど、とにかく初めて出会った。それはたしかだよね。じゃあ君の目的はなんだったんだろう。
誰かに対するっていうより、もっと漠然としたものへの復讐だったのか。それともただ単にむかついていただけなのか。わからない。あのとき、君の顔に「怨恨」とは書いてなかった。「むかつく」とも書いてなかった。じゃあ、なにが君を突き動かしたんだ?
俺の彼女は君に嫉妬していた。返り血を浴びる勇気がなければ復讐なんてできない、相手が誰だろうと。台所でひとり包丁を振り回すのが関の山だ。彼女は君に勝てないと思った。だから出ていったんだ。
そんなわけで、俺はいまひとりだ。バンドを抜けて、女とも別れて、いろんな意味でひとりだ。でも孤独とは違う。孤立でもない。孤高だ。どんなに落ち込もうと、俺は孤高だ。それを君に知ってほしかった。
ねえ君。もういちど聞く。本当に君は俺と面識のない人間なのか。たまたま俺がレジに入ったから俺を傷つけただけで、俺でなくても、誰でもよかったのか。
もちろん俺は君を知らない。だからきっと、君も俺のことを知らない。でもひょっとすると、それは単なる俺の決めつけかもしれない。
警察署で俺はなんども防犯カメラに写った君の画像を見た。見せられた。なんども繰り返し見ているうちに、変な話だけれど、君と馴染みになったような錯覚に陥った。完璧な赤の他人とは思えなくなってしまったんだ。そして無性に君に会いたくなった。変か? 変だな。それは認める。俺は変だ。
君は俺の、それなりに安定した日々を見事にぶち壊してくれた。でもね、あれはみんな、ぶち壊れてよかったものだ。安定をぶち壊すのがロックンロールだからだ。人間、守りに入ったら死んだも同然だ。俺は君を恨んでない。いや、まじで。
ところで俺は、君にお釣りの三百四十円を返していない。それを返すまでは、俺にとっての事件は終わらない。だから返す。返してやる。
抜糸をして、包帯を解いて、傷はふさがった。多少の痛みは残っている。雨の日なんかは特に、傷痕が引きつって、てのひらが痺れる。だけどギターを弾くぶんには問題ない。むしろ痛みが俺をエキサイトさせる。この痛みが俺であり、君なんだ。
中指の付け根から手首にかけて、まっすぐに引かれた白い線。新しい手相みたいだ。本屋で立ち読みして調べたら、運命線といってこれは強運のしるしなんだそうだ。
俺をアホだと思うか。そうだ、アホだ。でも俺はこう思うことにしている。
「俺に起こることは、俺を殺さないことなら、それがなんであろうと俺を強くする」
元ネタはニーチェだ。
俺はいま、アコースティックギターを持って鶴見駅前で歌ってる。夕方の六時から九時まで。バイトがない日は終電まで歌ってる。君は知ってるだろうか。駅前に「コンビニ傷害事件の目撃者を捜しています」と看板が立っている。あの横で歌ってるのが俺だ。
投げ銭入れのギターケースに、いつでも三百四十円は入れておく。見かけたら取ってくれ。それで貸し借りなしだ。
俺たちは再会する。俺は声をかける。君は応える。そこからなにが生まれるのか。わからない。どうなろうと、予測不能な未来に、俺はぞくぞくする。
つ
つくねんと
10/05/03
つくねんと
何をするでもなく、ただひとりじっとしている様子。
つくねん。
駅のホームでつくねん。
コンビニの駐車場でつくねん。
新宿の地下道でつくねん。
上野の西郷さんの前でもつくねん。
どこにいてもつくねん。
俺。
気がつけばほうけて。途方にくれて。光はいつも斜め上から、人を見下げて。どんなに着込んでようと裸に剥かれて。
俺のいる場所、六畳一間。爪切り、耳掻き、歯ブラシ。なにもねえ。窓にカーテンもねえ。陽射しは容赦なく、俺の影、真後ろの壁に落ちて、焦げ付くまで。
そう言えば俺は自分の眼で自分の背中を見たことがないのだった。死ぬまで見ることはないだろう。それが俺という人間の不完全さの証明なのだ。でもこれは俺に限ったことじゃない。
なにもない部屋。コンビニ弁当を食べて、殻だけが残って。箸の先に付いた飯粒に陽が当たって、ひりひり、かわいていく。俺もかわいてきた。
畳にさす光。畳の目ひとつひとつ、やけにくっきりとして、ささくれて、けば立って。長年、俺の体から剥がれ落ちた細胞が死んで畳の目に染み付いているから、この六畳は俺の肉体だとも言える。俺が去っても俺そのものとして部屋は残るのだ。俺以上に存在の輪郭をくっきりさせて。
板場で包丁を研いでる俺。
配電盤を開いて接続を点検してる俺。
戦闘服で匍匐前進する自衛隊員の俺。
ストリート・ミュージシャンとしてつまらない脚光を浴びてる俺。
あの時ああしていればこうなっていた俺が世界のいたるところに遍在する。その俺らがいっせいにへたりこむ。つくねんとしてしまう。
嘘をつくねん。
餅を搗くねん。
舟が着くねん。
霊が憑くねん。
なにさらすねん。
むかしむかし、『あしたのジョー』の矢吹丈は力石徹の死亡記事を前に連日つくねんとしてまるで死んだようだったが、業を煮やした丹下段平に「どこまで堕ちれば気がすむんだ」とどやされ「ここまでだ」とひと言、死亡記事を破いて立ち上がったのだった。その場面にいたく感動した子供の俺は大人になり「ここまで」と言える地点まで堕ちていこうとしたものの「どこまで?」と言ってくれる他人がいなければ「ここまで」と言えるきっかけもなく、ずるずると堕ちていくだけなのだった。
「どこまで?」誰も言ってくれないのなら自分で言うしかない。「どこまで?」
「ここまで」俺は答えるだろう。
奈落の深さに比べたら人間一個の堕落なんてたかが知れてる。まして俺のすること。
だから自分で言うのだ、「どこまで?」と。さあ、言え。
そう念じながらいまだ、つくねんとしている。
「ここまで」と言える、あと一歩の距離が永遠に遠い。