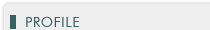みんな、最初は、ぜんぜんだめだった。。
久田恵さんの巻。
2008/10/17
中学2年と小学5年のふたりの娘に、
子育てというほど、たいしたことはしてません。
面倒なことは、ほとんど妻まかせ、
だめな父親だなあと思うだけで、なんにもしないんですけど、
3つだけ、
「けがと病気に気をつけるように」
「事故と事件にも巻きこまれないように」
それから、
「将来は仕事をもって、女性でも経済力をつけるように」
ということを、ときどき、いうようにしています。
娘たちは、
1つめ、2つめのことはともかく、
3つめのことは、あんまりピンとこない様子ですけど、
ま、大きくなってからピンとくればいいかと思って、
わたしの話をちゃんと聞いてくれそうなタイミングを見はからって
いいきかせてるんです。
そんなこという当のわたしの経済力が心もとないということは
たなにあげてますが。。。
で、
わたしが娘たちにそんなこというのは、
女性は、
男性よりもたくさん、
いろんなことを乗り越えなくちゃ仕事をつづけられない、
と思うからです。
いまのよのなか、
女性がずっと仕事をつづけて、
自力で生計を立てられるほどお金を稼ぐのは、まだまだたいへんだけど、
娘たちには、なんとかそれをやってみてほしいんですね。
久田恵さんは
ノンフィクションの書き手として、
『フィリピーナを愛した男たち』(文藝春秋)で
1990年に大宅壮一ノンフィクション賞を受賞、
いまもって活躍をつづけている女性です。
最近では、
『私の仕事 私の生き方』という文藝春秋の季刊誌(2007年)にも
「女と仕事――そして『定年』後」
という題でエッセイを発表しています。
思えば、私は団塊世代である。
同級生の男たちが、いよいよ定年期に突入して、これからなにをしようか、と考え始めているこの人生の節目に(フリーランスの私は定年とは無縁の立場だけれど)、一人の女として、「働いて、稼いで、自立して生きたことが誇りだ、後は、時々、楽しいことがあればもうなにもいらない」という境地に至っている自分に驚いている。(同書147ページ)
もちろん、
久田さんがいまにいたるまでには、
山あり谷ありだったと思います。
久田さんは
ノンフィクションの仕事をなりわいとするまでに、
あれやこれや、いくつも仕事を経験してるんです。
......そう、思い出すのも大変なほど、私はさまざまな仕事をして生計を立ててきたのだった。
その「変転」は、「素手で、自力で、人生を切り開く!」と、一通の書き置きを残して家出をした二十歳の時から始まった。
つまりは、女がそんな無謀なテーマを持ってしまうと、めまいがするほどめまぐるしく生きざるを得ないわけで、私はそんな世代の女の一人だったのである。
トランジスター工場の女子工員に始まり、ウエイトレス、パン屋の店員、スーパーの試食販売、人形劇団員、フリーの人形遣い、放送ライター、東販の伝票整理、区役所のアルバイト、家庭教師、知人の家の賄い、キャバレーの衣装係、舞台照明の助手、業界雑誌記者、広告会社嘱託、サーカス団の炊事係、女性誌ライター......。
どう考えても、行き当たりばったり。
脈絡がない。ほとんど闇雲である。(同書146ページ)
でも、
面白いのは、
いろんな仕事を転々とするなかでも、
若い久田さんがへんに落ち込んだりせずに、
すごく元気に毎日を暮らしていたんじゃないかと
思えることです。
久田さんが仕事を転々としていたのは、
高度成長時代の終わりのころですけど、
もし、いまの若い人たちが、
こんなふうにころころと仕事をかえて暮らしているとなると、
将来不安がどうとか、最低賃金がこうとか、
なんとなく暗い感じになっちゃうんじゃないでしょうか。
久田さんは暗い感じで仕事を転々としてなかった、
ということがわかるのは、
たとえば、
エッセイ集『愛はストレス』(文藝春秋、1996年)で、
その仕事のなかみについて、
こんなふうに披露しているからです。
ふと思いついて人形劇団をつくり......埼玉や千葉などを地図を片手に車で走り、保育園や幼稚園を見つけると、車を止めて訪問し、園長先生に「子どもたちに夢を」などと言って仕事をとるのである。
私立の保育園や幼稚園の園長先生には基本的に人柄の良い人が多い。
「まあ、お若いのに......」
「素敵なお仕事ですこと」
などと言って、ともかく話を聞いてくれて、一日回ればなんとか二つ、三つの園で「一公演、二万円から一万五千円」の仕事の契約がとれたのである。......儲かりはしなかったが、なんというか遊んでいるような働いているような、そんなわけのわからないお金の稼ぎ方が実に良かったのである。(同書86~87ページ)
そんな久田さんも、
子どもが生まれてから、
どうやって仕事をつづけるか、つづけないのか、
ずいぶん悩んだ時期があったそうです。
初めての著書
『母親が仕事をもつとき』(学陽書房、1982年)
を書き終えたとき、
久田さんは夫と別れ、
ひとりで働きながら子どもを育てることになった
といいます。
私はフリーのライターという不規則な仕事をしていたこともあり、保育園だけではとてもおさまらず、一時は、友人、知人、ベビーシッター、と子どもを預けまくって育てた。
「おかあさん、今日は、ボクをどこに預けるの?」
そう聞いた幼い息子の声が、いまも聞こえるようで、子どもの情緒が少しでも不安定になったりすると、あの時、この時のあれこれを思い出し、きっと私が悪いんだ、と罪悪感にさいなまれたことも多かった。それは、働く母親なら誰でも経験する心境でもあるが、この内面化された「母性神話」から私もなかなか解放されなかったのである。(同書文庫版あとがき、296~297ページ)
それでも、
息子さんが12歳の中学生になったとき――
入学祝のCDプレーヤーでビートルズなんか聞いている彼の横顔を見ていたら、ふと、長かった子育ても一段落したなあ、と肩の荷が少し下りたような気がして、ふと、言ってみたことがあった。
「ねえ、おかあさんはずっと仕事をしていて、小さい時からあなたにずいぶん苦労かけたのよね」
その時である。息子はビートルズを聞きながらのどかに答えたのだった。
「小さい時の苦労なんか覚えてないよ。だけど、ボク、おかあさんと一緒で結構、面白かった」
その「面白かった」の一言がどれほど胸にしみたことか。(同書文庫版297ページ)
わたしは
久田さんに取材で合計4回、
お目にかかったことがあります。
3年前、
4回目の取材のときにいただいた名刺には、
片面にお名前だけ、
ひっくり返すと、
ご自宅の住所とともに
「花げし舎」
と刷ってありました。
久田さんが自宅を拠点に「花げし舎」を主宰して、
人形のお芝居の公演をしたり、
いろんなことをいろんな人たちと
はじめたんですよと、
楽しそうにおっしゃっるので、
わたしも楽しい気持ちになって、
自分もなにかはじめてみようと思ったのでした。