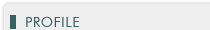みんな、最初は、ぜんぜんだめだった。。
重松清さんの巻。
2008/08/18
学校の先輩とか、会社の上司とか、
目上の人から若いころの話を聞かされたうえに、
「だれだって苦労してるんだ」
「おれも努力してここまで来たんだ」
なんて言われると、
素直に耳をかたむける気はしなくなるでしょう。
このブログでも、
「最初は、だめだった」という話を
教訓じみないように伝えるのは、なかなかむずかしいですが、
でも、
そもそも、
そういう苦労話って、
先輩や上司はともかく、
最近の有名人からは
なかなか見つからないんですよ。
たとえば、
一昔前のスポーツの有名選手なら、
長嶋茂雄選手がデビュー戦で4打席4三振だったとか、
ガッツ石松選手は世界チャンピオンになるまでに
10回以上も負けたことがあったとか、
だめ話のエピソードが
ついてまわっていたんじゃないかと思います。
ひるがえって、
最近のスポーツ選手には、
わたし、そんなだめ話、あんまり知りません。
重松清さんも、
『セカンド・ライン』(朝日新聞社、2001年)
で同じようなこと書いてます。
......たとえばサッカーの中田選手や野球のイチロー選手、あるいは女性なら宇多田ヒカルさんでもいいのだが、不思議なくらいエピソードが少ないことに気づかされる。彼らのすごさを強調する材料はいくらでもあるが、彼らがいかにしてヒーローになったかについては、ほとんど伝わってこないのだ。
だからこそ、彼らは「ヒーロー」よりも、むしろこう呼ばれることのほうが多い。
天才――。(同書36ページ)
で、
そういう重松清さんも、
いまのように作家として大活躍するまでのエピソードが
ほとんど知られてないと思うんですけど、
重松さんのエッセイやコラムをたくさん収録した同書のなかに、
いくつか語られていました。
大学卒業後、
出版社に就職した重松さん。
その会社をすぐ辞めているんだそうです。
......ぼくはサラリーマン生活にわずか十一カ月で見切りをつけた。すでに結婚をしていたので、なにはともあれ飯を食うために働かなければならない。てっとりばやくフリーライターの仕事を始めてはみたものの、二十二、三歳の駆け出しに仕事がどんどんまわってくるほど、この業界も人材が払底しているわけではない。半年もしないうちに「こりゃあヤバいなあ......」と就職雑誌に手を伸ばすはめになってしまった。(同書223ページ)
わたしは、
重松清さんが「田村章」や「岡田幸四郎」というペンネームで
雑誌原稿3000本を書き、
また、
「ゴーストライターの帝王」と呼ばれて
単行本100冊も書いた、
という話を耳にしたことはありますが、
そんなふうに名うてのライターになるまでに
「ヤバい」時期があったとは、知りませんでした。
重松さんは、
そのヤバい時期、
大学時代の同級生――「相棒」のような間柄だったSさんに、
『女性自身』の仕事で救ってもらったといいます。
駆け出しの、しかもまだ二十三歳の若造ライターが老舗の週刊誌で原稿を書くチャンスを与えられた理由は、じつにかんたんなことである。ぼくの学生時代の友人――いまに至るまで最もたいせつな友人・Sが、『女性自身』編集部に在籍していたのだ。
学生時代から、なにをやるにもコンビを組んできたぼくたちだった。毎晩のように酒を飲み、(中略)飲み屋で見知らぬ奴らと大立ち回りをしたり、薬師丸ひろ子の駅貼りポスターを盗みに行って西武池袋線の電車に撥ねられそうになったり、ビニ本の局所に塗られた墨をマーガリンでこすって消したり、SMごっこと称して大学の同級生を椅子に縛りつけてキャンパス内に放置したり......バカなことばかりやってきた。
そんなコンビの片割れが、せっかく入った出版社を一年たらずで辞めて、新婚間もない妻のヒモ同然の暮らしをしているのを見かねたのだろう、Sは「ウチの仕事をやってみないか?」と声をかけてくれたのだ......(同書231~232ページ)
ところが、
『女性自身』の仕事の紹介をきっかけに、
重松さんはSさんと、
学生時代のようには話せなくなってしまいます。
仕事を受ける側とまわす側の関係が、
重松さんとSさんのなかに、でてきたからです。
一九八九年の年明け、ひさしぶりにSと会社の外で会ったときに「フリーの生活はどうだ?」と訊かれた。その頃のぼくはフリーライターとしてじゅうぶんに生活は成り立っていたが、まだSの仕事をあてにしなければ多少不安な、そういう中途半端な時期だった。いつもならためらうことなく自慢話を披露する傲慢なぼくが、そのときはSに気を遣った。駆け出し時代の恩を忘れてはいないからと言いたくて、ことさらに苦労と感謝を強調した。「おまえがいなかったらアウトだったよ」と芝居がかったことを言い、「フリーになんかなるもんじゃないさ」と媚びたふうに笑った。
Sは黙ってうなずくだけだった。
そして、その二カ月後、黙って自ら命を絶った。
会社の仕事に行き詰まり、フリーになることも心の片隅で考えながら、いやそれでも俺は会社の中でしか生きられないんだと自分に言い聞かせたすえの決断だった――と通夜の席で知った。(同書224ページ)
それからも重松清さんは、
『女性自身』を中心にライターの仕事をつづけ、
その一方で小説も書きはじめます。
そして、
山本周五郎賞や直木賞など、
文学賞をつぎつぎと受賞して大活躍となりますが、
いちばん最初に受けたのは坪田譲治文学賞で、
対象となった本は
1999年の中編作品集『ナイフ』(新潮社)でした。
その『ナイフ』のなかの、
「エビスくん」という作品、
これが、
小学6年生の「ぼく」と転校生の「エビスくん」の物語、
相棒の物語なんです。。
「エビスくん」を書くのは、ほんとうにキツかった。すぐに立ち止まり、へたりこみそうになる主人公の背中をどやしつけながら、物語を紡いでいった。それは、ぼくにとってのリハビリテーションだったのかもしれない。
「エビスくん」は、小説としての出来不出来はともかくとして、いまに至るまで、ぼくのいっとう好きな作品である。一編の末尾近くの言葉――「会いたいなあ」は、物語からはみ出した、ぼく自身の声だった。「どこにおんねや、きみはいま」は、Sに向けた言葉でもあった。(先の『セカンド・ライン』225ページ)
わたしも、
わたしの中学2年の娘も、
重松さんの本のなかでは『ナイフ』がいちばんで、
とくに「エビスくん」を愛読しています。
どうして、この作品に引かれるのか、
やっとわかった気がします。