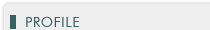みんな、最初は、ぜんぜんだめだった。。
藤沢周平さんの巻。
2008/07/22
わたしの会社も住まいも、
東京の練馬区の
大泉学園という町にあります。
妻の実家もこの町にあります。
で、
おばあちゃんちと味噌汁の冷めない距離
のところに住めば、
まあいろいろ好都合ということで、
結婚後、大泉在住15年です。
都心から電車で30分。
駅前からつづく桜並木は
春になるとすごくきれいですし、
近くには映画館もフィットネスクラブもあるし、
おいしい食べものやさんとかケーキやさんもたくさんあるし。
いまでは、
この町がすっかり気にいりまして、
なにか用事でもないかぎり、都心にはでていきません。
いつも大泉で
ぶらぶらしてるんです。
あるとき、
取材で有名な翻訳家の方とお会いして、
そんなふうに大泉で暮らしてますという話をしたところ、
「いい町ですよね、藤沢周平さんも住んでらっしゃいますしね」
といわれて、へえっ! と思ったんですね。
藤沢さんの本は読んだことありましたが、
近くにお住いとは、知らなかった。。。
で、
藤沢さんの時代小説ではなく、
エッセイ集『小説の周辺』(文春文庫、1990年)
を買って読んだら、
朝の十時になると、私は喫茶店に行くために家を出る。私が住むGという町は、にぎやかなところは表のバス通りだけで、まわりにはまだ畑や芝生が残っているような場所である。そこで喫茶店に行くにも、バス通りをずっと北に歩いてSという店に行くか、反対側の南に歩いてスーパーの中のJという店に行くかということになるのだが、家の者はSはともかく、私がJに行くのをあまり好まない。
というのはJはコーヒー専門店ではなくて、アイスクリームやたこ焼きも売っているからだ。つまり子供向けの店なので、代金の支払いは品物と引き換えになる。コーヒーはSが二百八十円、Jは二百円である。そういうこととか、私が子供たちにまじって、カウンターの止まり木でコーヒーをすすっている恰好がはなはだいかさないとかいうことが、家の者に嫌われる理由のようである。(同書71ページ)
そこでわたしも、
藤沢さんみたいにSやJという店で
コーヒーを飲んでみたら、
なにかちょっとひらめいたりするんじゃないかと思って。
大泉の町をうろうろ、
それらしき店を探しまわったことがありました。
(でも見つかりませんでした。。)
藤沢さんは出身地の山形で
中学校の先生をしていましたが、
20代なかばで結核にかかり、
その手術と療養のために東京にでてくることに
なったのだそうです。
そして、
ようやく結核の療養所を退院した藤沢さん、
山形へもどったものの、
すでに年齢は30歳。
「病み上がり」の人だとも見られてしまい、
再就職がうまくいきません......。
ちょうどそのころ、東京から一枚のハガキが来た。それは病院とは無関係の、Oさんという東京に住む知人からのハガキで、Oさんはその中に、小さな業界紙の仕事がひとつあるが働いてみないかと書いていた。私は東京にもどって、その業界紙に勤めた。私はそのころ、働いて金をもらえるなら、日雇い仕事もいとわないという気持になっていた。私はそのとき三十歳だった。三十になって職もなければ金もない、むろん住む場所も結婚する相手もいない、社会的には一人の無能力者にすぎなかったのである。
業界紙というものがどういうものか、皆目見当もつかなかったが、私は物を書く仕事だということに気持を惹かれた。日雇いよりは多少知的な感じがしたし、また書くことが嫌いでなかったからである。その小さな業界紙で、私は記事を書くだけでなく、あとでは広告取りもやらされたのだが、その仕事は予想以上に快適だった。新聞記事を書いているとき、私は少し大げさに言うと、自分を水を得た魚のように感じることがあった。(同書105~106ページ)
それからの藤沢さん、
44歳のときに「オール讀物」の新人賞を受賞、
46歳で直木賞を受賞して
47歳で会社をやめて作家の仕事に専念するようになり、
49歳のとき、1976年に、大泉に自宅をかまえたのでした。
でも、
さっきの『小説の周辺』のなかに、
こんなことも書いてあるんです。
好き嫌いは別にして、いちばん忘れがたい小説をあげるとすれば、私の場合やはり『オール讀物』の新人賞をもらった「溟い海」ということになろう。
三十代のおしまいごろから四十代のはじめにかけて、私はかなりしつこい鬱屈をかかえて暮らしていた。鬱屈といっても、仕事や世の中に対する不満といったものではなく、まったく私的な中身のものだった。私的なものだったが、私はそれを通して世の中に絶望し、またそういう自分自身にも愛想をつかしていた。
そういう場合、手っとり早い解消の方法として、酒を飲むとか、飲んだあげく親しい人間に洗いざらい鬱屈をぶちまけるやり方があるだろう。だが私は古い教育をうけたせいか、そういうやり方は男らしくないと考えるような人間だった。自分の問題は自分で処理すべきだと思っていた。当時はまだ、そういう考え方が出来る気力と体力があったのだろう。
さて、そういう気持のありようは、べつに小説に結びつくとは限らないわけだが、私の場合は、小説を書く作業につながった。
「溟い海」は、そんなぐあいで出来上がった小説である。......(同書188~189ページ)
小説を書きはじめるまでの人生のなかで、
藤沢さんは、
世の中に絶望するほどの、
どんな経験をしたんでしょう...。
若くして結核にかかったものの、
30代で業界紙に職を見つけて、
そこで「水を得た魚」みたいになっていたのに。。。
藤沢さんは
自分自身のことを語らない作家だったといいます。
でも、
60代になってから書いた自叙伝
『半生の記』(文藝春秋、1994年)のなかで、
業界紙に就職したあと、同郷の三浦悦子さんと結婚し、
その後、
わずか4年あまりで
悦子さんをがんで亡くしたと――
昭和医大病院では、医師も看護婦も親切だった。治療のしようもない病妻を献身的に看護してくれた。子供は田舎に預けたので、私はそこから会社に出勤し、夕方には病院に帰る生活をつづけた。しかしそれからふた月ももたず、昭和三十八年の秋に悦子は亡くなった。二十八歳だった。
そのとき私は自分の人生も一緒に終ったように感じた。死に至る一部始終を見とどける間には、人には語れないようなこともあった。そういう胸もつぶれるような光景と時間を共有した人間に、この先どのようなのぞみも再生もあるとは思えなかったのである。下宿で小人数の親しい人たちにあつまってもらって密葬を済ませ、田舎でする葬儀に帰るまでの間骨壺と一緒にいると、時どき堪えがたい寂寥感に襲われることがあった。(同書108~109ページ)しかし胸の内にある人の世の不公平に対する憤怒、妻の命を救えなかった無念の気持は、どこかに吐き出さねばならないものだった。私は一番手近な懸賞小説に応募をはじめた。そしておそらくはそのことと年月による慰藉が、私を少しずつ立ち直らせて行ったに違いない。昭和四十四年一月に、私は現在の妻高澤和子と再婚した。私はそのころ病弱な老母と幼稚園に通う娘をかかえて疲労困憊していた。再婚は倒れる寸前に木にしがみついたという感じでもあったが、気持は再婚出来るまでに立ち直っていたということだったろう。
......和子は私の家の状況を見さだめると、右に老母左に娘の手をひいて銭湯に連れて行き、車を呼んで病院に連れて行くことからはじめた。(同書109~110ページ)
『半生の記』のなかから
引用したこの文章には、
「死と再生」
という題名がつけられています。
藤沢さん、
「死と再生」の文章、
こんなふうに結びます。
先妻と死産の子供の骨を納めた墓は、高尾の墓地群の一角にある。すべて同型同規模と定められた墓である。そこに時どきお参りに行く。墓を洗い、花と線香を上げてから家内が経文をとなえる。お参りが済んで墓前の芝生でそなえた菓子などをたべ終わると、私は立ち上がる。墓地は丘の中腹にあって、そこから八王子の市街や遠い多摩の町町が見えるが、風景は秋の日差しに少し煙っている。
私と結婚しなかったら悦子は死ななかったろうかと、私は思う。いまはごく稀に、しかし消えることはなくふと胸にうかんでくる悔恨の思いである。だがあれから三十年、ここまできてしまえば、もう仕方がない。背後で後始末をしている妻の声が聞こえる。二十八だったものねえ、かわいそうに。さよなら、またくるからね。私も妻も年老い、死者も生者も秋の微光に包まれている。(同書110~111ページ)
藤沢周平さんが亡くなって
もう10年。
わたしの自宅から徒歩5分の大泉図書館には
藤沢さんの特設コーナーがあるんです。